10代 男性のご相談
表皮水疱症ってどんな病気?
症状チェックと対処法を皮膚科医が解説
⚠️まずは緊急度をチェック
◻︎ 発熱や感染の兆候がある
◻︎ 口腔・食道など粘膜にも症状(びらん・痛み)が出ている
◻︎ 創部が広く、水疱が破れて処置が難しい
◻︎ 食事がとりづらいなど栄養状態が心配
◻︎ 爪の変形や指の癒着など機能障害の進行がみられる
▶︎ 1つでも当てはまれば受診/オンライン相談を
友達登録は無料

医師の回答
ちょっとしたこすれで水ぶくれができちゃう先天性の皮膚疾患です

K.Hさん
体育の後やカバンのベルトが当たるだけで水ぶくれができ、破れるとしみて服も当てられません。口の中にもびらんが出ると食事がつらく、学校を休むこともありました。家族にうつるのか不安でしたが、医師から感染症ではないと説明を受けて安心しました。
受診して検査の流れを聞き、日常は摩擦を避ける服や寝具に変え、創部は低刺激の被覆材で保護・保湿を徹底。発熱や赤みの変化に注意して早めに相談するようにしました。処置のコツを覚えると、痛みや再発時の不安も少しずつ軽くなりました。
30秒セルフチェック/診断チャート
01
症状の出方・強さ
軽い摩擦・圧迫で水疱やびらんが出る
皮膚だけでなく口腔など粘膜にも症状が出ることがある
水疱が破れてびらん→痂皮になりやすい
02
経過・持続
乳幼児期から見つかりやすく、症状を繰り返す
瘢痕化や爪の変形、指の癒着などが進むことがある
03
随伴症状・背景
発熱や感染で悪化しやすい
家族歴があるなど遺伝性が示唆される
摩擦を受けやすい手足・関節部、口腔などに出やすい
結論
該当が多い:要受診
該当が少ない:迷う場合も早めに相談
友達登録は無料
表皮水疱症とは?
表皮水疱症(ひょうひすいほうしょう、Epidermolysis Bullosa:EB)とは、生まれつき皮膚や粘膜が非常に弱く、軽い摩擦や外的刺激で水ぶくれやびらんを生じる先天性の遺伝性疾患です。赤ちゃんや子どもに見つかることが多く、皮膚だけでなく口腔や食道などの粘膜にも影響することがあります。見た目は大きな水疱が目立ちますが、感染症ではないため他人にうつることはありません。病態は皮膚の「のり」に相当するタンパク質が遺伝子異常により欠損・不足することで、皮膚がはがれやすくなってしまう仕組みです。
たとえば、単純型は皮膚の表層で水疱が生じるため比較的軽症で、接合部型や栄養障害型は基底膜や真皮側まで深く障害され、瘢痕や栄養不良を伴いやすいとされます。水疱の深さや広がりによって重症度や合併症の危険性も異なります。
主な原因
遺伝子異常による接着タンパク質の欠損や構造異常
摩擦や圧迫など軽い外的刺激
発熱や感染による皮膚のもろさ増悪
慢性的な栄養不良による皮膚修復力低下
好発部位は手足や関節部、口腔内、食道などで、摩擦を受けやすい皮膚や粘膜が中心です。乳幼児期から症状が目立つことが多く、成長とともに手足の爪の変形や指の癒着など機能障害が進む場合もあります。
経過としては、初期には小さな水疱ができ、それが破れるとびらんや痂皮(かさぶた)となります。繰り返すことで瘢痕化や苔癬化〔たいせんか〕が進み、関節可動域の制限や手足の変形が起こり得ます。悪化因子には乾燥、摩擦、感染、発熱、栄養不足などがあります。早期から適切な創傷ケアや栄養管理を行うことで合併症を抑え、生活の質を守ることが重要です。
応急処置(今日できること)
泡立てた石けんでやさしく洗い、こすらない
破れた水疱は清潔なガーゼで保護する
保湿剤をこまめに塗布し乾燥を防ぐ
衣服・寝具はゆったり&低刺激素材を選ぶ
発熱や感染の兆候があれば早めに受診する
一般的な表皮水疱症治療に使われる薬
◆ ① 創傷・水疱の処置に使う薬剤・外用剤
薬剤・用品名 分類 特徴・使用目的
ゲーベンクリーム® 抗菌外用薬(スルファジアジン銀) 二次感染予防/びらん部に使用
バクトロバン®軟膏 抗菌薬(ムピロシン) MRSAなど限局感染に有効
ステロイド外用薬 抗炎症剤(ロコイド®など) 炎症・びらん部に少量短期間使用することも
ヘパリン類似物質外用薬 保湿剤 乾燥部位に使い、皮膚保護・保湿
ペプチド含有創傷治癒促進剤(リプロスキン®など) 上皮化促進 創傷治癒をサポート
外用麻酔剤(リドカインジェルなど) 疼痛コントロール 処置時の痛み軽減目的に使用されることも
創傷被覆材(ハイドロコロイド・フィルムドレッシング等) 保護・湿潤環境維持 非粘着性・低刺激のものを使用(例:メピレックス®・アクアセル®など)
◆ ② 内服薬・全身管理で使われる薬剤
分類 代表薬 使用目的・備考
抗菌薬(内服・点滴) セファレキシン、アモキシシリンなど 二次感染時/蜂窩織炎・敗血症などの予防・治療
鎮痛薬・NSAIDs アセトアミノフェン、ロキソニン®など 慢性的な痛み、処置時の疼痛管理に
鉄剤・造血因子 フマル酸第一鉄など 慢性出血・貧血の補正(重症型で多い)
栄養補助剤 ビタミン・ミネラル製剤 皮膚修復・全身状態維持(亜鉛、A・C・Eなど)
ステロイド内服 プレドニゾロンなど 難治性の炎症・瘢痕進行抑制目的に短期使用(まれ)
免疫抑制薬(難治例) シクロスポリンなど 重症症例に限定的に使用(副作用に注意)
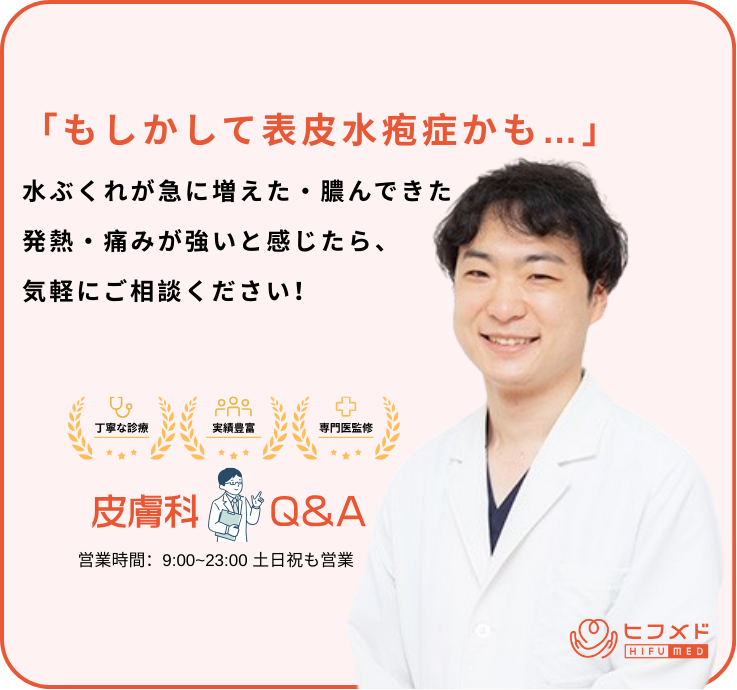
病院で何を調べるの?
視診・問診:皮膚の水疱やびらんの分布、粘膜症状の有無を確認します。発症時期や家族歴を聞き取り、病型を推定する初期の基本情報になります。
皮膚生検:局所麻酔下で小さな皮膚片を採取し、顕微鏡や免疫染色で障害の深さや欠損するタンパク質を確認します。結果が出るまでに数日を要し、小さな瘢痕が残ることがあります。
免疫蛍光抗体法(IFM):皮膚切片に抗体を用いて、特定の接着タンパク質の局在や欠損を可視化します。EBの病型分類に有用で、診断精度を高めます。
遺伝子検査:血液や粘膜からDNAを抽出し、異常のある遺伝子を同定します。確定診断に重要であり、家族への説明や将来の治療選択にも役立ちます。
血液検査:貧血や栄養状態、炎症の有無を評価します。慢性的な創傷や食事困難に伴う合併症を早期に把握する目的があります。
- 細菌培養検査:水疱やびらん部から採取し、二次感染の有無や菌種を確認します。抗菌薬の選択にもつながります。
「表皮水疱症」と似ている症状の病気(鑑別疾患)
接触性皮膚炎(かぶれ)
アレルゲンや刺激物で炎症&水疱 特定のものに触れた後/左右非対称で一時的
天疱瘡(てんぽうそう)
自己免疫が原因の水疱性疾患/中高年に多い 高齢者/皮ふ+口の中にびらん/血液検査と生検で診断
伝染性膿痂疹(とびひ)
細菌感染で水ぶくれ→かさぶた/子どもに多い 感染性/周囲にうつる/抗菌薬で改善することが多い
先天性魚鱗癬様紅皮症(ハーリクイン型など)
皮ふが極端に厚くてひび割れ、水疱も伴うことがある 出生直後から全身/遺伝性疾患として分類
類天疱瘡(るいてんぽうそう)
高齢者に多い自己免疫性の水疱/天疱瘡と似て非なる病態 高齢発症/皮膚に強いかゆみ/組織検査で診断
スティーヴンス・ジョンソン症候群(SJS)
薬剤や感染による全身の重度の水疱・びらん 急速進行・高熱/粘膜障害・目の異常なども併発
表皮水疱症の特徴をチェック!
◻︎ 発熱や感染の兆候がある
◻︎ 口腔・食道など粘膜にも症状(びらん・痛み)が出ている
◻︎ 創部が広く、水疱が破れて処置が難しい
◻︎ 食事がとりづらいなど栄養状態が心配
◻︎ 爪の変形や指の癒着など機能障害の進行がみられる
▶︎ これらに当てはまれば、「表皮水疱症」や関連する疾患の可能性があります
⚠️緊急度をチェック!
◻︎ 口腔・食道など粘膜に症状が及んでいる
◻︎ 創部が広く破れて処置に困る
◻︎ 栄養不良が心配・食事がとりづらい
▶︎ 1つでも当てはまれば受診/オンライン相談を
友達登録は無料
受診の目安(タイムライン)
当日〜翌日:発熱や感染の兆候がある
早めに受診:口腔・食道など粘膜症状、創部が広範で処置が難しい、栄養不良が心配
様子見可:全身状態が良好で、創部を清潔に保護できている小さな水疱
予防のポイント
摩擦・圧迫を避けるゆったりした衣服を選ぶ
綿やシルクなど低刺激の寝具・衣類を使う
洗浄は泡でやさしく、拭くときは押さえるように乾燥させる
保湿をこまめに行い乾燥を防ぐ
水疱が破れたら清潔なガーゼで保護
高カロリー・高タンパクの食事で栄養を補う
発熱や感染の兆候があれば早めに受診
学校や周囲へ病気を伝え、生活上の配慮を得る
FAQ
Q1. 検査は何をしますか?
Q2. 人にうつりますか?
Q3. どんな薬を使いますか?
Q4. 日常生活で気をつけることは?
Q5. 受診のタイミングは?
医師
山田 貴博 Yamada Takahiro
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
監修薬剤師/公衆衛生学修士
畔原 篤 Atsushi Azehara
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
執筆者
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






