30代 女性のご相談
尋常性疣贅【いぼ】ってどんな病気?
症状チェックと対処法を皮膚科医が解説
⚠️まずは緊急度をチェック
◻︎ 「なかなか治らない」「急に大きくなる」「出血を繰り返す」できもの
◻︎ 高齢者で新しく出現し、変化が速い皮膚のしこり・いぼ
◻︎ 性器まわりのいぼ状のできもの(性感染症の可能性)
◻︎ いぼが多発する/長引く(免疫低下が背景のことあり)
◻︎ 魚の目・胼胝などとの区別がつかない場合
▶︎ 1つでも当てはまれば受診/オンライン相談を
友達登録は無料

医師の回答
手や足にできる「いぼ」、
実はウイルスが原因です

C.Bさん
30秒セルフチェック/診断チャート
01
症状の出方・強さ
手指・足底・顔まわりなどに小さく硬い盛り上がり
表面がザラザラ/角質が厚い
黒い点状の血栓が見えることがある
02
経過・持続
単発〜多発。つながって大きくなることも
通常は痛み・かゆみは少ない(足裏は歩行で痛むことあり)
放置で数が増える/周囲に広がることがある
03
随伴症状・背景
小さな傷のあと、摩擦・蒸れやすい部位に出やすい
小児〜思春期に多い/免疫低下時に起こりやすい
魚の目・胼胝と紛らわしい
結論
該当が多い:要受診
該当が少ない:迷う場合も早めに相談
友達登録は無料
類天疱瘡とは?
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)とは、ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染によって皮膚に生じる良性のいぼの総称です。主に手指や足底、顔まわりに小さく硬い盛り上がりができ、表面はザラザラして角質が厚く見えるのが特徴です。多くは痛みがありませんが、足の裏のように圧力がかかる部位では歩行時に痛むことがあります。感染後すぐには症状が出ず、数週間から数か月を経て出現する場合もあります。
たとえば、手指の周囲にできる小型のいぼ、足底にできて歩くと痛む足底疣贅、顔や首にできる表在型のいぼなどが代表例です。いわゆる「魚の目」と似て見えることもありますが、黒い点状の毛細血管血栓がみられる点が特徴です。
【主な原因】
ヒトパピローマウイルス(HPV)の感染
傷ついた皮膚からのウイルス侵入
皮膚や物品を介した直接・間接接触感染
免疫力低下やストレスによる抵抗力の減弱
好発部位は手の甲、指先、爪の周囲、足の裏などで、摩擦や小外傷が生じやすい部分に多くみられます。小児から思春期に特に多く、またスポーツや立ち仕事などで足裏が蒸れやすい人、免疫機能が弱っている人にも起こりやすい傾向があります。
経過としては、初期は数ミリ程度の小さな硬い丘疹から始まり、放置すると数が増えたり周囲に広がったりすることがあります。掻破や摩擦で出血や痛みを伴う場合もあり、慢性化すると自然治癒には半年から数年以上かかることがあります。乾燥や蒸れ、免疫低下が悪化因子となるため、早期に皮膚科で診断と治療を受けることが再発予防や生活の質の改善につながります。
応急処置(今日できること)
いぼを引っかいたり、つぶしたりしない
触れた後は石けんで手洗いする
足裏は清潔に。乾燥・通気性のよい靴を選ぶ
家族とタオル・スリッパを共用しない/プール・体育館はサンダルを使用
気になるできものは早めに皮膚科で評価を受ける
一般的な尋常性疣贅治療に使われる薬
◆ ①【液体窒素療法(凍結療法)】★第一選択!
液体窒素(−196℃)を綿棒やスプレーで患部に直接当てる 最も一般的。週1回程度で通院治療が必要。痛み・水ぶくれを伴うこともあり
対象 手足・指・足底などのいぼ。皮膚科で実施
◆ ②【外用薬(塗り薬・貼り薬)】
角質溶解剤 サリチル酸 イボコロリ(市販)など 皮膚を柔らかくし、角質を除去。液体窒素と併用されることが多い
スピール膏(市販) サリチル酸含有の貼付剤 いぼ・魚の目に使われる。皮膚がふやけてはがれやすくなる
ヨクイニン(内服) ヨクイニンタブレット(漢方由来) いぼ体質改善・自然消退を助ける目的で補助的に使用
5-FU軟膏(保険外使用) フルオロウラシル軟膏 細胞分裂抑制薬(保険適応外)。医師管理下で処方されることもあり
イミキモド外用薬 ベセルナクリーム HPVに対する**免疫応答を高める外用薬(尖圭コンジローマ向け)**だが、難治性いぼにも一部使用(保険外)
◆ ③【その他の治療法】
炭酸ガスレーザー 局所麻酔のうえで焼灼。再発の可能性あり
エルビウムヤグレーザー/電気焼灼 難治例に。保険外もあり
注射療法(ブレオマイシンなど) 難治性いぼに使用されるが、痛みや副作用のリスクあり
活性化免疫療法(ドライアイス+免疫賦活薬) 実験的な方法も一部あり(保険外)
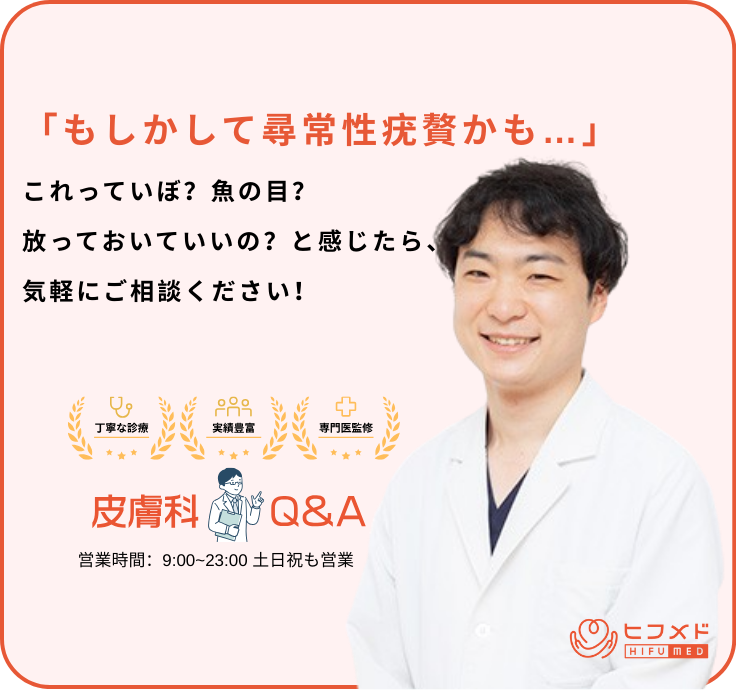
病院で何を調べるの?
- 視診・触診:いぼの大きさ、表面の性状、黒点の有無を観察します。魚の目や胼胝との鑑別に重要で、ほとんどの場合は視診で診断可能です。
- ダーモスコピー(皮膚鏡検査):拡大鏡を用いて血管の点状構造や角質の特徴を確認します。短時間で行え、痛みのない検査です。
- 皮膚生検:見た目が典型的でない場合や皮膚がんとの鑑別が必要な場合に行います。局所麻酔をして組織を採取し、数日〜1週間で病理診断が得られます。瘢痕が残る可能性があるため、必要時に限定されます。
- 細菌培養・真菌鏡検(KOH検査):二次感染や白癬との鑑別を行う際に使用します。採取した皮膚片や滲出液を顕微鏡や培養で調べ、数日で結果がわかります。
- 血液検査(免疫評価):いぼが多発・難治の場合、免疫力の低下が背景にあることもあるため、炎症マーカーや免疫状態の確認を行うことがあります。
「類天疱瘡」と似ている症状の病気(鑑別疾患)
鶏眼(けいがん)/魚の目
圧迫部位にできる/中心が固い角質で痛みあり 押すと痛い・芯がある/黒点はない/感染しない
胼胝(たこ)
慢性的な摩擦や圧迫で皮膚が厚くなる 周囲との境目がはっきりしない/痛みは圧で出る
脂漏性角化症
高齢者に多い/茶色っぽくてざらざらした“老化性いぼ” 感染なし/加齢とともに増加/色が濃いことも
皮膚がん(基底細胞癌・扁平上皮癌 など)
なかなか治らないできもの/出血・急に大きくなる 高齢者・急な変化・出血に注意
粉瘤(アテローム)
皮膚の下に袋状のしこり/におう液体が出ることも 触れるとやわらかい/押すと中身が出る/中心に開口部あり
皮膚線維腫(良性腫瘍)
小さな硬いしこり/色は肌色〜やや茶色 ウイルス感染ではない/拡大しにくい
ウイルス性のいぼ(扁平疣贅・糸状疣贅など)
尋常性以外にも多彩な形がある 顔や首に細長いタイプも/自己判断しづらい
伝染性軟属腫(みずいぼ)
子どもに多い/白くて中心がくぼんでいる プールなどで感染/水っぽくて柔らかい感じが特徴
梅毒性のいぼ(尖圭コンジローマなど)
性器まわりにいぼ状のできもの 性感染症/形や場所が特徴的/診断と治療は早めに!
類天疱瘡の特徴をチェック!
◻︎ 「なかなか治らない」「急に大きくなる」「出血を繰り返す」できもの
◻︎ 高齢者で新しく出現し、変化が速い皮膚のしこり・いぼ
◻︎ 性器まわりのいぼ状のできもの(性感染症の可能性)
◻︎ いぼが多発する/長引く(免疫低下が背景のことあり)
◻︎ 魚の目・胼胝などとの区別がつかない場合
▶︎ これらに当てはまれば、「類天疱瘡」や関連する疾患の可能性があります
⚠️緊急度をチェック!
◻︎ 高齢者で新しく出現・変化が速い
◻︎ 性器まわりのいぼ状病変
▶︎ 1つでも当てはまれば受診/オンライン相談を
友達登録は無料
受診の目安(タイムライン)
当日〜翌日:出血・急な増大・色形の急変がある/高齢者で新規のしこり・できもの/性器まわりのいぼ状病変
早めに受診:歩行で痛む足底いぼ/数が増える・広がる/鑑別がつかない
様子見可:小さく痛みが少ないが、増える・長引く場合は早めに相談を
予防のポイント
触れたら手洗い/つぶさない・引っかかない
足裏を清潔にし、通気性のよい靴に
タオル・スリッパの共用を避ける/プール・体育館はサンダル
小さな傷は早めにケア/睡眠・食事を整え免疫を保つ
気になるできものは早めに皮膚科へ
FAQ
Q1. 魚の目とどう見分けますか?
Q2. 放っておくと自然に治りますか?
Q3. 家族にうつりますか?
Q4. 市販薬で治せますか?
Q4. どんな検査をしますか?
医師
山田 貴博 Yamada Takahiro
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
監修薬剤師/公衆衛生学修士
畔原 篤 Atsushi Azehara
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
執筆者
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






