60代 女性のご相談
粉瘤ってどんな病気?

医師の回答
粉瘤は、皮膚の下に袋状の構造物ができ、角化物が袋の中にたまってできた良性の腫瘍のことです。

〜“しこり”の正体は、皮膚の下にたまった古い角質かも〜 半球状に盛り上がった皮膚の中央に黒っぽい開口部がみられることがあり、強く圧迫すると腐臭を伴うじゅくじゅくとした内容物が出てくることがあります。 自覚症状はありませんが、なかで破れると赤くなり、はれや痛みがあらわれます。全身のどの部位でもみられ、顔や首、胸、背中などによくみられます。
粉瘤(ふんりゅう)とは、皮膚の下に袋状の構造ができ、その中に角質や皮脂がたまることで生じる良性の嚢胞(表皮嚢腫〔ひょうひのうしゅ〕)です。全身どこにでも発生しますが、顔や首、背中、耳の後ろ、臀部などに多く見られます。触ると弾力のあるしこりとして感じられ、ゆっくりと大きくなっていくのが特徴です。表面に小さな黒い穴(開口部)が見えることもあり、炎症を起こすと赤く腫れて痛みや膿を伴うことがあります。自然に消えることは少なく、再発する場合もあるため、皮膚科での診断と処置が大切です。
粉瘤には「炎症を伴わない粉瘤」と「感染や炎症を伴った粉瘤炎」があります。前者はしこりとして経過しますが、後者は赤く腫れて強い痛みや膿を伴い、ニキビや脂肪腫と間違われることもあります。
【主な原因】
毛穴や小さな皮膚の傷から皮膚細胞が内側に入り込む
袋状の構造が形成され、その中で角質や皮脂が蓄積する
外傷やピアス穴、手術痕をきっかけに発生することもある
慢性的な刺激や摩擦が関与する場合もある
好発部位は手首、足首、腰、すね、背中などの皮膚で、さらに口の中、舌、頬粘膜、爪、頭皮にも見られます。中高年に多く発症し、男女差は明らかではありませんが、アレルギー体質や慢性疾患をもつ方に起こりやすい傾向があります。
経過は初期に赤紫色の発疹が出て強いかゆみを伴い、掻破によってさらに拡大します。悪化すると滲出やただれを起こし、長期化すると苔癬化(皮膚の肥厚や硬化)、色素沈着が残ることがあります。乾燥や摩擦、ストレス、感染、薬剤などが悪化因子となり、症状を慢性化させます。早期に受診し適切な治療を受けることで、症状の軽減や生活の質の維持につながります。
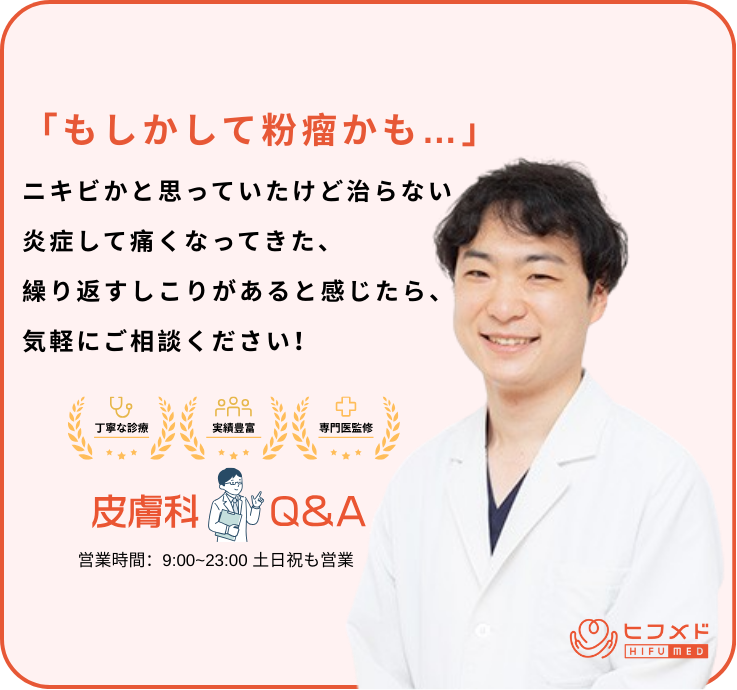
✅ 治療法
原則として自然に治ることはなく、根治には袋ごと除去が必要です。
◆ ①【炎症がない場合(非炎症性粉瘤)】
方法 内容
手術(小切開摘出術) 最も確実/袋(嚢腫壁)ごと完全に取る
くり抜き法(パンチ法) 5mm程度の器具で小さく穴を開けて内容物+嚢を除去/傷が小さいが再発もあり得る
◆ ②【炎症がある場合(炎症性粉瘤/感染粉瘤)】
方法 内容
切開・排膿+抗生物質 腫れて痛むときはまず膿を出して炎症を抑える
抗菌薬の内服・外用 セフゾン®、クラリス®、フシジン®軟膏など
→ 落ち着いたら手術 感染後に嚢腫壁が線維化する前に手術で摘出するのが理想
✅ 使用される薬剤(補助的)
分類 薬剤名 用途
抗菌薬(内服) セファレキシン(ケフレックス®)、クラリス®など 化膿した粉瘤の炎症を抑える
抗菌薬(外用) フシジン®軟膏、ゲンタシン®など 排膿後の処置に
鎮痛・解熱薬 ロキソニン®、カロナール®など 炎症時の疼痛対策
◆ 病院で何を調べるの?
視診・触診:粉瘤の位置、大きさ、炎症の有無を確認します。しこりの性状や開口部の有無を診て、他の腫瘍や脂肪腫との鑑別に役立ちます。
超音波検査:嚢胞の内部にたまった内容物や袋の構造を確認できます。非侵襲的で短時間に行えるため、炎症の有無や切除の必要性を判断する補助となります。
細菌培養検査:炎症や膿を伴う場合に行い、どの細菌が感染しているかを調べます。抗生物質選択の参考になり、治療の精度を高めます。
皮膚生検:しこりの診断が難しい場合や他の腫瘍との鑑別が必要な場合に行われます。局所麻酔下で組織を採取し、病理診断により確定診断が可能です。
血液検査:炎症が強い場合には、白血球数や炎症マーカー(CRP)を測定し、全身の炎症状態を把握します。とくに発熱を伴う際には有用です。
🔍 粉瘤と間違えやすい類似疾患(鑑別)
脂肪腫(しぼうしゅ)
⇒やわらかくて大きい/皮膚の下でゆっくり成長 袋がない/中心に黒点なし/押すとフニャっと動く炎症性粉瘤(化膿性アテローム)
⇒赤く腫れて熱をもつ/痛い 触ると熱感あり/自然排膿することも/悪臭あり基底細胞がん(皮膚がん)
⇒表面につや・カサブタ/治りにくい 出血しやすい/黒や灰色が混じる/皮膚がんの疑いがあれば生検尋常性疣贅(ウイルス性いぼ)
⇒表面がザラつくいぼ/足や手に多い 中心に黒点/皮膚模様が消える/ウイルス性なので拡がることも毛包炎(毛穴の炎症)/せつ・よう
⇒毛穴に一致して赤く腫れる/ニキビに似ている 膿点が中心/毛穴が関係している/比較的小さい皮膚線維腫
⇒固いしこり/押すとへこむ 長期間変わらない/痛みなし/黒点なし悪性黒色腫(メラノーマ)
⇒急に大きくなる黒っぽいできもの 色ムラ・形の左右差/出血・かゆみあり/要早期診断
予防のポイント 肌を清潔に保ち、過度な皮脂や角質の蓄積を防ぐ 摩擦や圧迫を避け、衣服や下着の締め付けに注意する ニキビやできものを自己処置で強くつぶさない ピアスや小さな外傷は清潔に管理し、炎症を放置しない 規則正しい生活で免疫力や皮膚の回復力を保つ 炎症やしこりに気づいたら早めに皮膚科を受診する 繰り返す場合は手術で袋ごと取り除くことを検討する
<参考資料>
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






