50代 女性のご相談
マダニ刺咬症ってどんな病気?

医師の回答
マダニ刺咬症は、山林や野原の草木に生息するマダニが皮膚に吸着して吸血することで生じる病気です。


〜山や草むらにひそむ、危険な小さな吸血生物にご注意を〜 マダニは皮膚表面を移動するため、からだのいたるところが吸血されます。吸血されると、赤い発疹[紅斑(こうはん)]、むくみ[浮腫(ふしゅ)]、出血があらわれます。かゆみや痛みなどの自覚症状はありません。 マダニが媒介する感染症には、ボレリアという細菌に感染することによって引き起こされるライム病(らいむびょう)、ウィルス感染症の重症熱性血小板減少症候群 (SFTS)、リケッチア感染症の日本紅斑熱などがあります。日本における発症数は少ないものの、マダニは日本にも生息しているため、注意が必要です。
マダニ刺咬症(ましこうしょう)とは、野山や草むらに生息するマダニに刺されることで生じる皮膚の炎症や感染症の総称です。マダニは人の皮膚に口器を深く差し込み、数日間にわたり吸血を続ける特徴があり、刺咬部は赤く腫れてかゆみや痛みを伴います。口器が皮膚に残ってしまう場合や、一部のマダニが重症熱性血小板減少症候群(SFTS)などの感染症を媒介することもあるため、注意が必要です。
たとえば、吸血部位の結節や腫れ、かゆみ、軽度の痛みなどが代表的で、発熱や倦怠感を伴う場合は感染症の可能性があります。媒介する感染症には、SFTS、ライム病、日本紅斑熱、Q熱、野兎病などがあります。
【主な原因】
マダニが皮膚に噛みつき長時間吸血すること
吸血中に唾液が皮膚内へ入り炎症を引き起こすこと
口器が皮膚内に残り、異物反応や感染を生じること
- 一部のマダニが病原体を媒介すること
蒙古斑はアジア人種、とくに日本人の新生児に非常に多くみられます。欧米人では比較的まれですが、アフリカ系の赤ちゃんでもよくみられることが知られています。出現部位は主におしりや腰、背中下部で、両側性に広がる場合もあります。
経過としては、生後から数年間で徐々に色が薄くなり、多くは就学前に目立たなくなります。まれに遷延性蒙古斑として思春期以降も残ることがありますが、生活に支障をきたすことはほとんどありません。乾燥や摩擦、日焼けなどで悪化することはなく、基本的に進行する病変ではありません。気になる場合には皮膚科で鑑別や経過観察を行うと安心であり、早期に正しい診断を受けることで不要な不安を軽減できます。
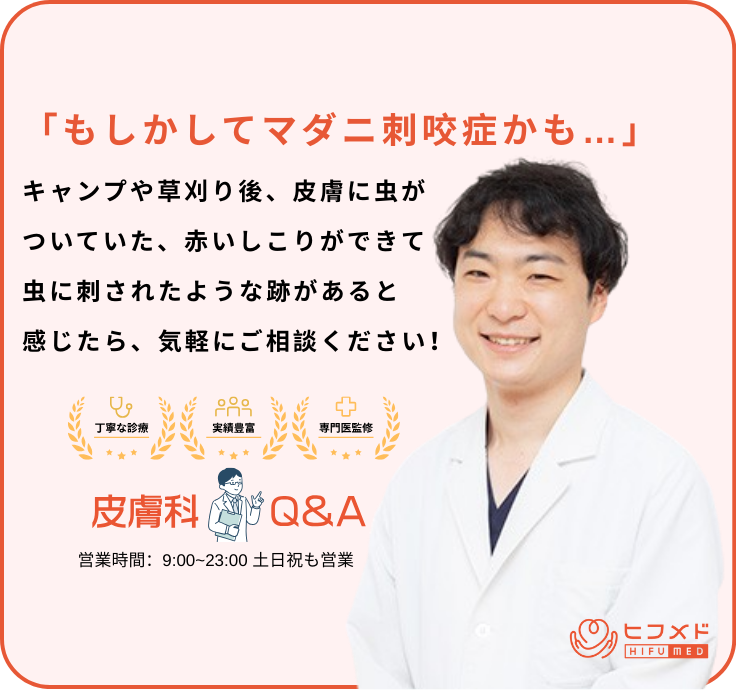
✅ 使用される薬剤
分類 薬剤名 目的
抗生物質(内服)
・ドキシサイクリン(ビブラマイシン®)
・ミノサイクリン(ミノマイシン®)
リケッチア・ボレリア感染症の予防または治療
抗菌外用薬 ゲンタシン®、フシジン®など 刺し口の二次感染予防に
解熱・鎮痛薬 カロナール®、ロキソニン®など 発熱・痛みがある場合
◆ 病院で何を調べるの?
視診・問診:刺咬部位の腫れや発赤、口器残存の有無を確認します。アウトドア歴や発症時期も重要で、感染症の可能性を判断する第一歩です。
皮膚局所処置後の病理検査:切除した皮膚とともに口器を確認することで、残存の有無や炎症像を確定できます。瘢痕リスクは小さいですが、結果までに数日を要することがあります。
血液検査:白血球数やCRPなど炎症マーカーを確認します。SFTSを疑う場合は血小板数や肝機能を調べ、全身症状の程度を把握します。
感染症特異的検査:ライム病では抗体検査、日本紅斑熱ではPCRや抗体検査が用いられます。発症から一定期間後に有用性が高まります。
細菌培養:刺咬部から滲出液がある場合に行い、二次感染を起こしているかを確認します。抗菌薬選択の参考になります。
画像検査(必要時):リンパ節腫脹や臓器障害を疑う場合、エコーやCTを追加して合併症の有無を評価します。
🔍 マダニ刺咬症と間違えやすい類似疾患(鑑別)
蚊・ブヨ・ノミ刺症
⇒一時的な赤み・かゆみ・腫れ 虫体がついていない/かゆみが強く、すぐ反応が出るツツガムシ病
⇒高熱+刺し口のかさぶた+発疹/ダニ媒介感染症 発熱・全身倦怠感あり/血液検査で確定蜂刺症(ハチさされ)
⇒急な激痛・腫れ/アレルギー反応あり 刺された瞬間に強い痛み/アナフィラキシーに注意毛虫皮膚炎
⇒細かい赤いブツブツ/かゆみ強い/季節性 虫体なし/集団で発症しやすい/毛が原因有棘紅斑(ゆうきょくこうはん)
⇒血管炎 痛みを伴う紅斑/血管性反応 虫体なし/左右対称/発熱を伴うことも膿痂疹(とびひ)・毛包炎
⇒かゆくてジクジクした赤みや膿 水ぶくれや膿が出る/接触で広がる
予防のポイント 山や草むらでは長袖・長ズボンを着用する ズボンの裾を靴下に入れ、首元や手首も覆う 虫よけスプレーを衣服や皮膚に使用する 帰宅後すぐに入浴し全身をチェックする ペットの毛や皮膚も定期的に点検する 刺された場合は自分で取らず医療機関で処置を受ける 発熱や倦怠感があれば速やかに受診する 草刈りやキャンプの際は事前に予防策を徹底する
<参考資料>
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






