40代 女性のご相談
悪性黒色腫ってどんな病気?

医師の回答
悪性黒色腫(メラノーマ)は、皮膚の色素をつくるメラノサイトという細胞ががん化して起こる皮膚がんの一種です。


〜ホクロみたいな黒いしみ、それ、実は「皮膚がん」かもしれません〜
悪性黒色腫とは、メラニンを作る「メラノサイト」という細胞ががん化した皮膚がんの一種です。
進行が速く、命に関わる可能性もある悪性度の高いがんです。悪性黒色腫(メラノーマ)とは、皮膚の色素を作るメラノサイトががん化し、黒や茶色のしみやホクロに似た腫瘍を生じる皮膚がんの総称です。進行が速く転移しやすい性質を持ち、命に関わる可能性があるため、早期発見と治療が極めて重要とされています。日本人では特に足の裏や手のひら、爪の周囲に多くみられることが特徴です。
代表的な病型として、足底や手掌、爪甲下に多い「末端黒子型」、顔や体幹に多い「表在拡大型」、結節状に盛り上がる「結節型」、高齢者の顔に生じやすい「悪性黒子型」などがあります。いずれもホクロやしみと見分けがつきにくいため注意が必要です。
主な原因
紫外線によるDNA損傷
足底や手掌での慢性的な摩擦や圧迫
既存のホクロからの変化
家族歴や遺伝的要因
加齢や免疫力低下
好発部位は足の裏、手のひら、爪の周囲、顔、背中などで、日本人では特に足底や手掌に多くみられます。発症しやすい人として、家族に皮膚がんの既往がある方や、ホクロの数が多い方、高齢者が挙げられます。
経過は、初期には小さな黒色斑として現れ、徐々に大きさや色が変化します。悪化すると腫瘍が盛り上がり出血し、リンパ節や内臓に転移することがあります。慢性化すれば全身に影響を及ぼすため、紫外線・摩擦・外傷などの悪化因子を避けつつ、早期に皮膚科を受診することで生活の質を大きく守ることができます。
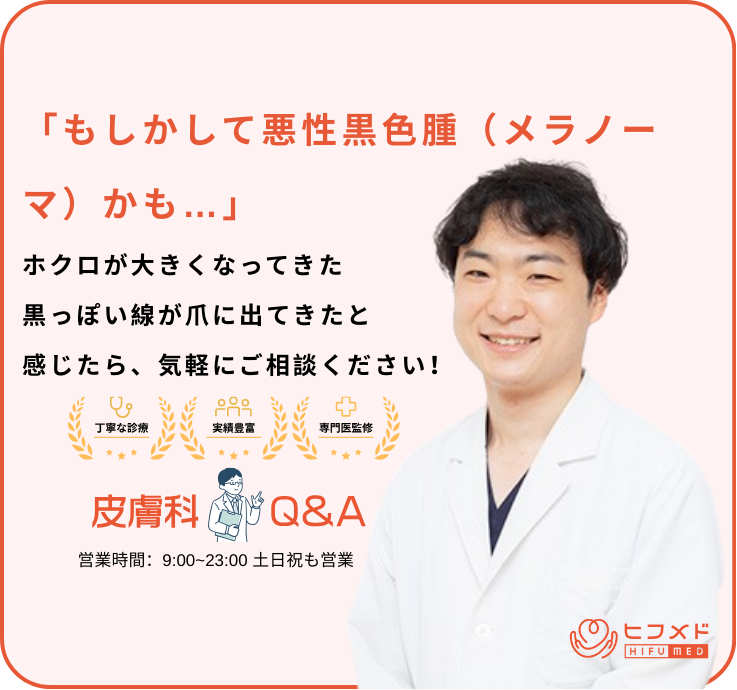
✅ 治療に使われるお薬・治療法
◆ ① 外科的切除(基本治療)
腫瘍とその周囲の皮膚(2〜3cm)を広めに切除
状況によってセンチネルリンパ節生検+リンパ節郭清を行う
◆ ② 進行・転移例での薬物療法(保険適用)
分類 薬剤名 特徴
免疫チェックポイント阻害薬
・ニボルマブ(オプジーボ®)
・イピリムマブ(ヤーボイ®) 免疫反応を活性化し、がん細胞を攻撃させる/奏効率・生存率が大きく改善
BRAF阻害薬 ダブラフェニブ(タフィンラー®) BRAF遺伝子変異陽性例に有効(欧米人に多い)
MEK阻害薬 トラメチニブ(メキニスト®) 上記と併用されることが多い
抗PD-L1抗体 アテゾリズマブ(テセントリク®)など 免疫治療薬の一種
🔬 病院で何を調べるの?
視診・問診:皮膚科医がホクロやしみの形・色・大きさ・経過を確認し、悪性の可能性を推測します。患者本人や家族からの発症経過も重要な情報になります。
ダーモスコピー検査(皮膚鏡):拡大鏡を用いて皮疹の色調や血管パターンを詳しく観察します。ホクロとメラノーマを鑑別する際に役立ち、外来で迅速に行えます。
皮膚生検:局所麻酔を行い腫瘍の一部を切除して顕微鏡で確認します。確定診断に不可欠で、結果は数日〜1週間程度で判明します。瘢痕が残る可能性も説明されます。
血液検査:炎症マーカーや腫瘍マーカー(LDHなど)を測定します。進行度の把握や全身状態の評価に役立ち、治療前後の比較にも用いられます。
画像検査(CT・MRI・PET):リンパ節や内臓への転移を調べます。手術の範囲や治療方針を決定するために行われ、進行例では欠かせません。
- リンパ節センチネル生検:腫瘍付近の最初にリンパが流れ込むリンパ節を確認し、転移の有無を調べます。病期分類や治療方針に直結します。
🔬 間違えやすい他の病気(鑑別)
疾患名 特徴 見分けポイント母斑細胞母斑(ほくろ)
⇒生まれつき or 年齢とともに増える黒い斑点 対称・境界明瞭・色が均一/変化しなければ良性の可能性が高い脂漏性角化症(老人性いぼ)
⇒年配に多い茶色〜黒の盛り上がり/ざらつきあり 数年かけてゆっくり大きく/触ってポロッと取れるような表面基底細胞癌
⇒皮膚がんの一種/黒や赤/ツヤがあり潰瘍になる 大きくなっても転移しにくい/表面が光沢あり青色母
⇒黒い色の深めのほくろ/真皮にメラニンがある 小さく変化がない/日本人に多い良性斑爪下出血(線状出血)
⇒爪の下にできる茶~黒いスジ/外傷などが原因 一定期間で爪と一緒に伸びる/変化がなければ問題なし血管腫(被角血管腫など)
⇒赤黒いできもの/出血しやすい つまむと少しへこむ/血管が関係/加齢性の変化が多い
予防のポイント 日焼け止め(SPF30以上)を毎日使用する 強い日差しを避け、帽子や衣服で紫外線を防ぐ 足裏・手のひら・爪のホクロの変化を定期的に観察する 鏡や家族の協力で背中や見えにくい部位もチェックする ABCDEルール(形・境界・色・大きさ・変化)を意識して確認する 摩擦や圧迫が繰り返される部位のホクロに注意する 怪しいしみやホクロを見つけたら早めに皮膚科を受診する 家族歴がある場合は特に定期的な検診を受ける
<参考資料>
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






