60代 男性のご相談
菌状息肉症ってどんな病気?

医師の回答
菌状息肉症(きんじょうそくにくしょう)は、皮膚にできるリンパ腫(皮膚T細胞リンパ腫)の一種で、がんの一種にあたります。

〜「ただの湿疹」と思ったら…実は皮膚のリンパ腫かもしれません〜
菌状息肉症とは、皮膚にできるT細胞性リンパ腫(皮膚T細胞リンパ腫)のひとつで、がんの一種です。
湿疹や皮膚炎のような症状から始まり、時間をかけて進行することが特徴です。菌状息肉症(きんじょうそくにくしょう)とは、皮膚に発生するT細胞性リンパ腫(皮膚T細胞リンパ腫)の代表的な疾患で、がんの一種です。湿疹や皮膚炎のような症状から始まるため初期には見分けが難しく、長期にわたって進行するのが特徴です。皮膚に限局している段階では治療が可能ですが、進行するとリンパ節や内臓に及ぶことがあります。特に40代以降の男性に多い傾向が報告されています。
たとえば、初期には紅斑期と呼ばれる赤い斑点や湿疹様の皮疹が出現し、次第に盛り上がって肥厚したプラーク期へ進行します。さらに進むと腫瘤期となり、皮膚に結節ができ、リンパ節や内臓にも転移することがあります。別名として「皮膚T細胞リンパ腫」と総称されることもあります。
主な原因
皮膚に存在するTリンパ球の異常な増殖
免疫調節の異常
遺伝的要因の関与
ウイルスや環境因子が背景にある可能性
顔・体幹・四肢に紅斑やプラークが出やすく、慢性湿疹と区別がつきにくいことがあります。なりやすい人としては中高年の男性が多く報告されますが、女性にも発症し得ます。
経過は、初期の紅斑期から肥厚期、さらに腫瘤期へと段階的に進みます。初期にはかゆみを伴い、掻破や乾燥によって悪化します。進行すると苔癬化(たいせんか)や腫瘤形成が目立ち、リンパ節や内臓に波及することもあります。乾燥・紫外線・摩擦・感染などが悪化因子となりやすく、早期に皮膚生検で診断し適切な治療を受けることが生活の質の維持につながります。
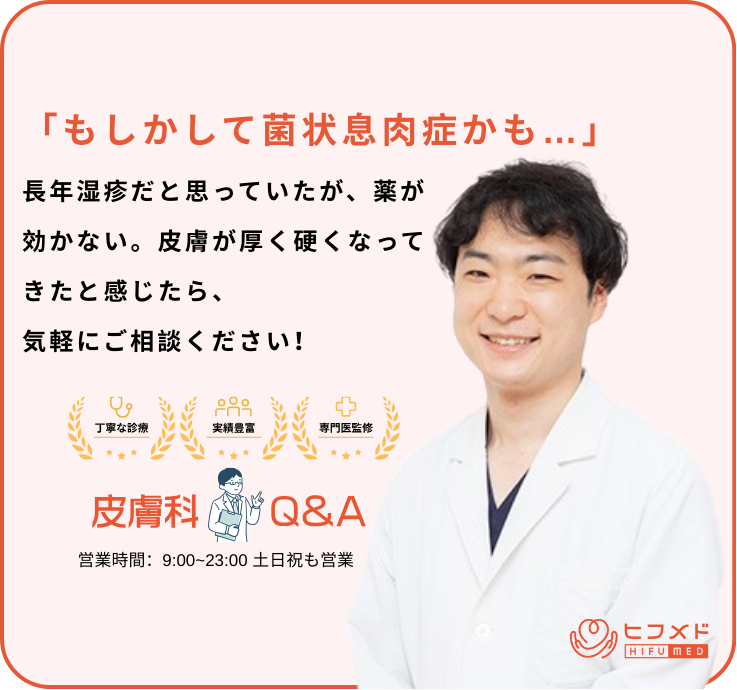
✅ 治療法(病期別)
◆ 初期(紅斑期~プラーク期)
治療 内容
外用ステロイド 軽症例では皮膚炎として対応可
光線療法(ナローバンドUVB / PUVA) 病変部位に紫外線を照射/再燃の可能性あり
タルモゲン療法(外用化学療法) ニトロゲンマスタードなど使用(国内未承認も多い)
◆ 中等度~進行期(腫瘤期以降)
治療法 内容
全身化学療法 CHOP療法など/全身に進行した場合
ヒト型抗体療法(抗CCR4抗体など) モガムリズマブ(ポテリジオ®)=CCR4陽性のCTCLに保険適用
インターフェロン療法 免疫調整作用による進行抑制
ベキサロテン(レチノイド製剤)内服 細胞分化促進作用/皮膚T細胞リンパ腫に保険適用あり
放射線療法 局所病変に使用/効果的な症例あり
造血幹細胞移植(稀) 若年・再発難治例で考慮される場合あり
🔬 病院で何を調べるの?
視診・問診:皮疹の形や分布、経過を詳細に確認します。湿疹や乾癬との鑑別に重要で、長期経過や薬剤反応性を聞き取ります。診察時点での病型を把握するのに役立ちます。
皮膚生検:皮膚の一部を局所麻酔で採取し、病理組織を調べます。Tリンパ球の異常な増殖や腫瘍性変化が確認できます。結果が出るまで数日〜1週間程度かかり、小さな瘢痕が残ることがあります。
血液検査:腫瘍マーカー、リンパ球の異常、炎症反応などを調べます。特に末梢血に腫瘍性細胞が出現していないかを確認します。経過観察や治療効果判定にも活用されます。
画像検査(CTやPET-CT):リンパ節や内臓への進展を調べる目的で行われます。進行期の診断や治療方針決定に不可欠です。被曝があるため、必要に応じて選択されます。
ダーモスコピー(皮膚鏡検査):紅斑やプラークの微細構造を観察します。腫瘍性病変の特徴を把握し、皮膚生検部位の決定に役立ちます。非侵襲的で外来でも容易に実施可能です。
- 細菌培養・真菌検査:二次感染が疑われる場合に行い、かゆみや滲出液の背景要因を特定します。適切な抗菌薬選択に寄与します。
🔬 間違えやすい他の病気(鑑別)
疾患名 特徴 見分けポイント乾癬(かんせん)
⇒銀白色のウロコ状の厚い皮ふ/左右対称に出やすい かゆみ軽度/肘・膝・頭部によく出る/爪の変形ありアトピー性皮膚炎
⇒子どもや若者に多い/乾燥・赤み・かゆみ 左右対称/アレルギー体質あり/家族歴など慢性湿疹
⇒長期間続く赤み+皮むけ+かゆみ ステロイドで一時的に改善/部位や左右差に注目扁平苔癬
⇒紫がかった小さなブツブツ/口の中にも出ることあり 強いかゆみ/光沢あり/口腔病変がヒントヴィダール苔癬(慢性単純性苔癬)
⇒かゆくて掻きすぎて皮ふがゴワゴワに 単独の部位に限局/長年続く/心理的ストレス関与も皮膚白癬(たむし)
⇒カビ(真菌)感染/円形で赤みがあり、ふちが盛り上がる 抗真菌薬で改善/KOH検査で診断可能
予防のポイント 低刺激性の保湿剤で毎日皮膚を保湿する 紫外線を避け、日焼け止めや衣服で皮膚を保護する 強いかゆみがある場合は掻き壊さず、薬でコントロールする 衣服やタオルは摩擦の少ない素材を選ぶ 感染を避けるために皮膚を清潔に保つ 規則正しい睡眠とバランスのよい食事を心がける ストレスや過労をため込まないよう生活を整える 定期的に皮膚科を受診し、変化があれば早めに相談する
<参考資料>
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






