40代 男性のご相談
尋常性疣贅【いぼ】ってどんな病気?

医師の回答
尋常性疣贅はいわゆる「いぼ」のことで、小さな傷からヒトパピローマウイルスに感染することで起こります。全身のどの部位でもみられますが、とくに手足や指に多く見られます。


〜手や足に硬くてザラザラした“できもの”、それはウイルス性のいぼかもしれません〜
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)は、ウイルス(ヒトパピローマウイルス:HPV)によって起こる皮ふのいぼです。
表面がザラザラ・ゴツゴツしていて、皮ふの盛り上がりがみられます。
最初は小さなポツっとしたできものですが、
放っておくと大きくなったり数が増えたり、他の場所にうつることもあります。
尋常性疣贅(じんじょうせいゆうぜい)とは、ヒトパピローマウイルス(HPV)というウイルスが皮膚に感染してできる「いぼ」のことです。このウイルスは非常に身近に存在しており、皮膚に小さな傷があると、そこからウイルスが侵入し感染します。感染してもすぐに症状が出るとは限らず、数週間〜数ヶ月かけて、皮膚の表面が徐々に盛り上がって「いぼ」として目に見えるようになります。
このいぼは、最初は小さなブツっとしたできものですが、放置しておくと少しずつ硬くなり、数が増えたり、大きくなったり、さらには体の別の部位や他の人にうつってしまうこともあります。表面はザラザラ・ゴツゴツしており、一般的には痛みやかゆみはありませんが、足の裏などにできた場合は歩くたびに痛みを感じることがあります。よく「うおのめ(魚の目)」と間違われますが、土踏まずやかかとなどにできたものの多くは実はいぼであることが多いです。
いぼができやすい部位は、手の甲、指、爪のまわり、足の裏や指、かかと、ひじ、ひざなど、皮膚がよくこすれる場所です。特に子どもや学生など皮膚がやわらかく活発に動く人、素足で生活することが多い人、手荒れやさかむけがある人、また体調不良やストレスなどで免疫が落ちている時などは感染しやすくなります。プールやジム、公共のシャワー室など湿った場所を素足で歩くこともリスクになります。
治療せずに自然に治るケースもありますが、治癒までに半年〜数年かかることもあり、拡大や再発、他人への感染リスクを考えると、早めの治療が望ましいです。
いぼの再発や拡大を防ぐためには、日常の予防ケアも重要です。手荒れや傷を放置せず保湿ケアをしっかり行い、プールやジムではスリッパを使用しましょう。また、いぼを触らない・ひっかかないことも感染拡大を防ぐポイントです。家族にいぼがある場合は、タオルや爪切りの共有を避けるようにしましょう。
「これ、いぼかな?うおのめ?ニキビ?」と迷った場合は、自己判断せずに皮膚科で正確な診断を受けることが大切です。見た目は似ていても、それぞれ治療法が異なります。
✅ 尋常性疣贅に使われる主なお薬・治療法
① 【外用薬(塗り薬)】
▶ サリチル酸(角質溶解剤)※第一選択の外用治療
スピール膏(処方・市販) サリチル酸 角質を柔らかくしてウイルス感染部位を除去しやすくする。毎日貼り替える。
イボコロリ(市販) サリチル酸液剤 塗るタイプ。乾かして保護膜を作る
🔸 サリチル酸だけではウイルスを殺せませんが、角質を軟化させて徐々に削ることでいぼが自然に脱落します。
▶ 活性化ビタミンD3外用薬(保険適用外の使い方)
カルシポトリオール ドボネックス軟膏など 本来は乾癬用。HPVに対する免疫応答促進の効果ありとされ、一部皮膚科で使用される
② 【内服薬(補助的)】
▶ 免疫調節・抗ウイルス作用が期待されるもの(保険適用外)
ヨクイニン(漢方) 皮膚のターンオーバーを促進、いぼ治療の補助に広く使用される
シメチジン 胃薬だが、免疫を調節する働きがあるとされ小児のいぼに試みられることがある(効果は限定的)
③ 【皮膚科で行う標準治療(薬以外)】
液体窒素(凍結療法) -196℃の液体窒素を綿棒やスプレーで患部に当てて凍結→壊死→脱落を繰り返す。最も一般的。
電気焼灼・レーザー焼灼 大きないぼ・しぶとい場合に行うが、瘢痕が残ることも
モノクロロ酢酸・トリクロロ酢酸外用 医療用の腐蝕剤。処方薬ではなく、医師が塗布。
④ 【新しい・補助的な治療法】
免疫療法(局所・全身) イミキモド(オフラベル)、BCGワクチン局所注射など
活性化NK細胞療法などの研究的治療 保険外、再発や多発例で考慮されることもあり
❌ 効果が期待できない薬の例
抗菌薬(ゲンタシンなど):ウイルス性なので効果なし
ステロイド軟膏:かえって悪化のリスクあり
ハイドロキノン・美白剤:無効
✅ 市販薬の例(軽症~初期なら試せる)
スピール膏 サリチル酸 貼るタイプの定番、広く使用可
イボコロリ液 サリチル酸 塗るタイプ、手足に使用可
ヨクイニンタブレット ヨクイニンエキス 長期補助的に使用されることあり
✅ まとめ:尋常性疣贅の治療薬・治療法
外用薬 サリチル酸(スピール膏・イボコロリ)、活性型ビタミンD3軟膏(医師判断)
内服薬 ヨクイニン(漢方)、シメチジン(補助的)
医療処置 液体窒素凍結療法(標準)、焼灼療法、免疫療法
市販薬 サリチル酸製品(スピール膏など)、ヨクイニン製剤
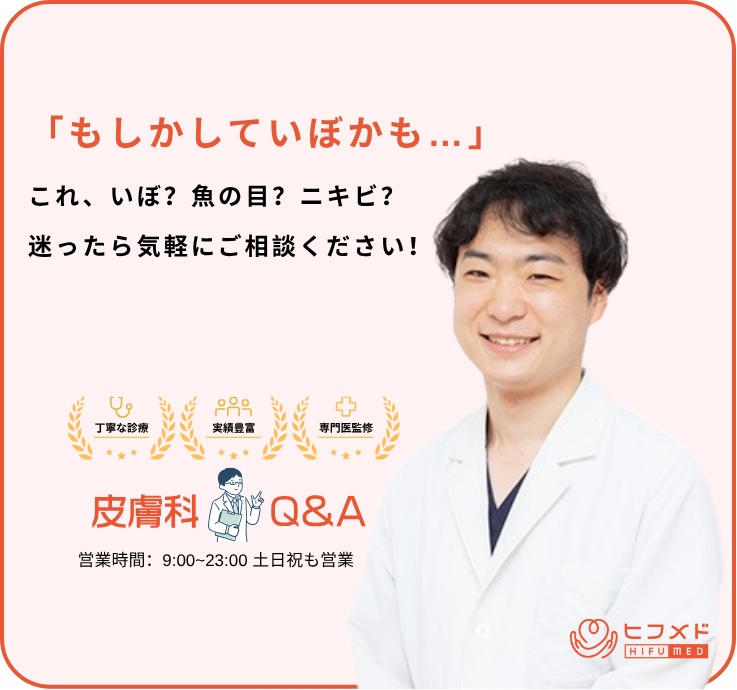
🔬 病院で何を調べるの?
病院での診察の流れ
問診:できた時期、広がり、痛み・かゆみの有無、他の人との接触歴などを確認
視診+ダーモスコピーで特徴を確認
必要なら検査(病理検査)
治療方針の説明(液体窒素、外用薬、漢方など)
🩺 間違えやすい「いぼっぽい」病気(鑑別疾患)
鶏眼(うおのめ)
⇒足裏にできる硬いしこり/中心に芯がある ウイルス性ではない/削ると芯が明瞭/痛みが強い
胼胝(たこ)
⇒皮膚がこすれて厚くなる/痛みはない 表面はなめらか/盛り上がりは均一で中央に芯なし
伝染性軟属腫(みずいぼ)
⇒小児に多い/中央がへこんだやわらかい小さなブツブツ ウイルス性だが光沢あり・表面がつるんとしている
稗粒腫(はいりゅうしゅ)
⇒目元などにできる白く小さいつぶ/痛みなし 粉のような内容物が入っている/感染性なし
ボーエン病・皮膚がん類似
⇒高齢者のいぼ様病変/ゆっくり拡大 硬く・ただれる・出血・変形などの変化あり/要生検
◇ 皮膚科での診断・検査
・ ダーモスコピーで表面構造や点状出血の有無を確認
・ 皮膚切除や病理検査が必要な場合もあります(がんの除外など)
・ 「削ってみたけど治らない…」という方はぜひ皮膚科へ!
◇ 治療方法(症状や年齢に応じて選択)
液体窒素療法 「凍らせる」定番治療/1~2週間おきに数回通院が必要
外用薬(サリチル酸など) 自宅でコツコツ塗って軟化・はがす/軽症例向き
レーザー治療 頑固な場合/美容目的含む(自由診療のこともあり)
局所注射・免疫療法 難治例や多発例/特殊な治療法が必要になることも
◇放置・自己処理のリスク
放っておくと周囲にうつる(オートワクシネーション)
自分で削る・ハサミで切る → 感染・悪化の原因に!
足裏の場合は歩くたびに刺激 → 深く硬くなって治療困難に
家族や友人にも感染する可能性があるので注意!
◇こんな場合は、お気軽に皮膚科へご相談ください!
- 「いぼ」かどうかよくわからない
- 治療してもなかなか治らない・再発する
- 子どもが気にして触ってしまう/広がってきた
- 足裏で痛みがあり歩きにくい
- がんなど悪性の可能性が心配な場合
→ 診断+状態に合った治療で、早めの改善を目指しましょう!
<参考資料>
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






