50代 女性のご相談
白板症ってどんな病気?

医師の回答
白板症は、口の中の粘膜にこすっても剝がれない白色の斑点があらわれる病気です。
〜お口の中や粘膜にできる「白いできもの」、それ白板症かも!?〜 白板症は、口の中の粘膜にこすっても剝がれない白色の斑点があらわれる病気です。
たばこやアルコールによる刺激、入れ歯や歯の詰め物などによる慢性的な刺激、ビタミンAやBの不足、
加齢や体質などが関連していると考えられていますが、原因は不明です。
白色の斑点は形や大きさがさまざまで、口の中の1箇所にできる場合もあれば、複数の箇所にできる場合もあります。
赤い発疹[紅斑(こうはん)]やただれ(びらん)を伴うと接触痛や食べ物による刺激痛が生じます。
白板症(はくばんしょう)とは、口腔粘膜にこすっても取れない白い斑や膜状の病変を生じる疾患の総称です。舌、歯ぐき、頬の内側、口蓋などに現れ、多くは無症状のため気づかれにくいことがあります。しかし、この病変は口腔がんへ進展する可能性がある「前がん病変」とされ、注意が必要です。初期には痛みや違和感が乏しく、歯科健診で偶然見つかることもあります。
たとえば、舌や口底にできるタイプは特にがん化リスクが高いとされ、また紅斑を伴う紅斑併発型、境界が不明瞭な広範囲型、表面がざらつきや肥厚を示す病型などがあります。白板症は良性の粘膜変化と考えられつつも、進行型や不整形のものは悪性化との関連が指摘されています。
【主な原因】
長期の喫煙による慢性的刺激
飲酒習慣による粘膜負担
入れ歯や歯の不整合による機械的刺激
栄養不足(ビタミンA・鉄など)
ヒトパピローマウイルス(HPV)の関与が疑われる場合
好発部位は舌の側縁や口底、頬粘膜、歯肉などで、特に舌と口底はがん化しやすい部位とされています。発症しやすいのは50歳以上の男性で、喫煙歴のある方に多く、また長年口腔内の違和感を放置している方にみられます。
経過は数か月から数年にわたり緩徐に拡大し、初期は白い膜状病変のみですが、悪化すると赤みやただれを伴い、しこりや圧痛が加わることもあります。慢性化すると上皮が厚くなり、がんとの鑑別が重要となります。乾燥、機械的摩擦、喫煙継続、ストレスなどが悪化因子となりやすいため、早期に医療機関で評価を受けることが、口腔機能や生活の質を保つために大切です。
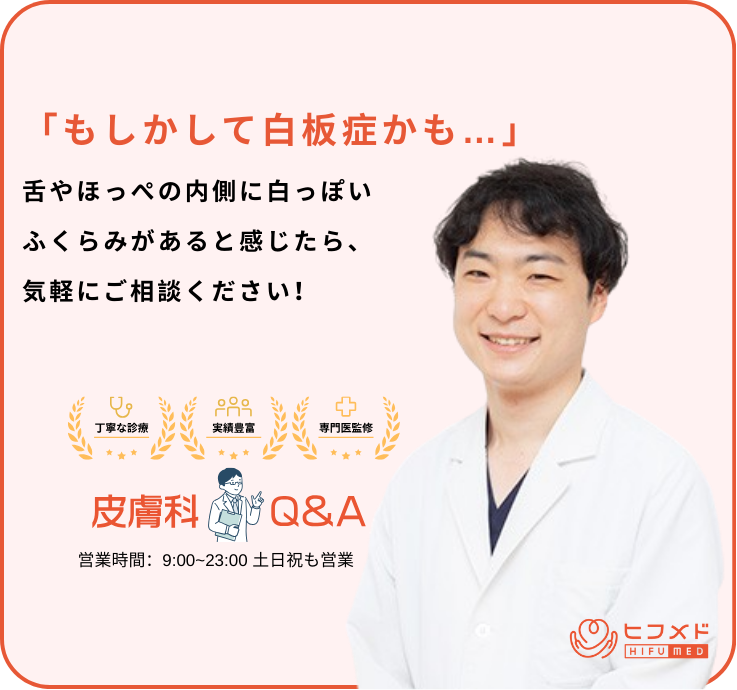
✅ 治療法(異形成の有無・程度によって対応が異なる)
◆ ①【軽度~中等度異形成】の場合
原因除去 禁煙・禁酒・慢性刺激の除去(義歯の調整など)
経過観察 数ヶ月ごとに再評価/改善がなければ切除検討
外用薬 通常は無効(外用治療では改善しないことが多い)
◆ ②【高度異形成・上皮内癌 or 進行傾向あり】の場合
外科的切除(標準治療) メス・CO₂レーザー・電気メスなどによる切除
レーザー蒸散 領域に応じて適応(再発率やがん化リスクの評価必要)
定期的な病理評価 切除後もがん化や再発リスクのあるため経過観察必須
◆ 病院で何を調べるの?
- 視診・触診:口腔粘膜の白色斑の有無や範囲を直接確認します。舌や頬の硬さ、圧痛の有無を触れて評価します。日常診察で行われ、経過観察の基盤となります。
- 口腔内写真・ダーモスコピー:病変を記録・拡大観察することで、色調や表面の変化を詳細に確認します。定期的に比較することで進行の有無を判断できます。
- 病理組織検査(生検):局所麻酔下で病変の一部を切り取り、顕微鏡で細胞異型やがん化の有無を確認します。結果判定には数日かかり、小さな瘢痕が残る可能性があります。
- 細胞診:ブラシで粘膜を擦過して細胞を採取し、異常細胞の有無を調べます。簡便で侵襲が少ない反面、生検に比べ診断精度は劣るため補助的に行われます。
- 血液検査:鉄欠乏や栄養状態を評価し、背景因子の把握に役立ちます。併存疾患の確認や治療方針決定にも用いられます。
- HPV検査:一部の白板症で関与が疑われるウイルスの検出を目的とします。必要に応じて追加され、がん化リスクの評価に参考となります。
🔍 白板症と間違えやすい類似疾患(鑑別)
口腔カンジダ症(カビ)⇒白い苔状の膜/こすると取れる 免疫低下・抗生剤使用中に多い/痛みや赤みもある
扁平苔癬(へんぺいたいせん)
⇒白くレース状に広がる/炎症あり 左右対称/表面が網目状/赤みやただれを伴う
ニコチン性口内炎
⇒硬口蓋(上あご)に白くなる/喫煙者に多い 点状の赤みが混じることも/タバコの影響強い
慢性刺激による角化症
⇒入れ歯・歯のこすれによる白い変化 原因除去で改善/部分的に一致する
口腔扁平上皮癌
⇒白〜赤の斑点→しこり・潰瘍に進行 しこり感・出血・潰瘍/長期間変化があるものは要検査
梅毒の粘膜病変
⇒口腔内に白い斑点・潰瘍/第2期梅毒で出ることも 性接触歴あり/血液検査で確認
予防のポイント
禁煙を徹底する
飲酒を控える
入れ歯や詰め物を適切に調整する
口腔を清潔に保つ習慣を続ける
定期的に歯科・口腔外科で健診を受ける
白い膜や違和感を自覚したら放置せず受診する
栄養バランスのとれた食生活を心がける
舌や頬の慢性的な摩擦を避ける
<参考資料>
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






