10代 女性のご相談
点状角質融解症【足ペタ病】ってどんな病気?
症状チェックと対処法を皮膚科医が解説
⚠️まずは緊急度をチェック
◻︎ 強い痛みや発熱がある
◻︎ 点状というより「傷・潰瘍・壊死」に近い見た目がある
◻︎ 糖尿病などがあり、足の傷が悪化している(足壊疽・膿瘍が疑われる)
▶︎ 1つでも当てはまれば受診/オンライン相談を
友達登録は無料

医師の回答
点状角質融解症は、足裏の皮膚の浅い部分が細菌に感染することで発症する病気です。「足ペタ病」ともいわれます。 原因となる細菌は数種類ありますが、高温多湿の環境下で細菌が増殖し、角質を溶かす物質を産生することで角質層を破壊します。
足のうらが白くふやけてペタペタ・においも気になる
それ、「足ペタ病」かもしれません
高温多湿な環境では、足の裏にいる細菌が増えやすくなります。
これらの細菌は、角質(皮ふの表面のかたい部分)を溶かす成分を出すことで、
皮ふの表面を傷つけてしまいます。
その結果、足の裏に数ミリほどの小さなへこみ(穴)がたくさんできてしまい、
悪臭がしたり、歩くと痛みを感じることもあります。
特に、足に汗をかきやすい人に多く見られる症状です。

Y.Rさん
部活で毎日スニーカーを履きっぱなし。ある日、足の裏が白くふやけてザラザラし、点々と穴のような凹みが増えました。においも気になって、家族にも指摘されるように。水虫かと思って市販薬を試したけれど、変化はなく不安でした。
オンラインで相談すると、点状角質融解症の可能性が高いとのこと。外用の抗菌薬を指示どおり使うと数日で楽に。靴をローテーションし、乾燥と通気を心がける大切さを知りました。同じ症状でも原因が違うことがあると学びました。
30秒セルフチェック/診断チャート
01
症状の出方・強さ
足裏が白くふやけてベタつく/ザラザラする
数ミリの小さな「点状の穴」が多数みられる
悪臭や歩行時の不快感・痛みがある
02
経過・持続
高温多湿の時期や長時間の靴着用で悪化する
汗をかきやすい・ムレやすいと再発しやすい
03
随伴症状・背景
通気性の悪い靴・靴下を使っている
学生・スポーツ・立ち仕事などで靴時間が長い
「水虫かな?」と思ったが改善しない(真菌ではなく細菌が原因のことが多い)悪臭や歩行時の不快感・痛みがある
結論
該当が多い:要受診 該当が少ない:迷う場合も早めに相談
友達登録は無料
点状角質融解症とは?
点状角質融解症(てんじょうかくしつゆうかいしょう/通称「足ペタ病」)は、足裏の皮膚が細菌に感染して発症する皮膚疾患の一つで、特に足の裏が白くふやけてペタペタ・ザラザラとした感触になり、無数の小さなへこみ(点状の穴)が現れるのが特徴です。
悪臭や歩行時の不快感を伴うこともあり、足のにおいや湿りが気になる人に多く見られます。主な原因は、汗やムレによって角質層が柔らかくなった状態に「コリネバクテリウム」などの細菌が感染し、細菌が角質を溶かす物質(酵素)を出すことで角質層が破壊されることにあります。
特に高温多湿の環境で細菌は増殖しやすく、通気性の悪い靴や靴下、長時間の靴の着用がリスクを高めます。発症部位は、足の裏、特に指の付け根から前足部に多く、指の間にも見られることがあります。足を洗ってもザラザラ感や悪臭が取れず、「水虫かな?」と間違われることも少なくありませんが、点状角質融解症は真菌ではなく細菌による感染症です。
この病気は特に汗っかきな人や学生、スポーツをする若年層(特に男子)、立ち仕事や接客業などで長時間靴を履くことが多い人に多く見られ、梅雨から夏場にかけて悪化しやすい傾向があります。
治療には、抗菌薬の塗り薬(例:クリンダマイシン、ナジフロキサシンなど)が用いられ、重症や再発を繰り返す場合には内服薬を併用することもあります。適切に治療を行えば、数日から1〜2週間程度で改善するケースがほとんどです。
再発予防には、毎日の足のケアと清潔保持が重要です。
具体的には、足を1日1回以上洗ってしっかり乾かすこと、吸湿性・通気性の良い靴下(綿素材や吸湿繊維)を使用すること、靴は毎日ローテーションで履き替えて内部を乾燥させること、靴の消臭・抗菌スプレーを活用すること、またジムや学校などでスリッパや足拭きマットの共用を避けることが挙げられます。
「足の裏が白くなってベタベタする」「においが強くなった」「小さな穴がたくさんできている」などの症状がある場合は、点状角質融解症の可能性があります。早めに皮膚科を受診することで、スムーズに治療を進めることができます。
応急処置(今日できること)
- 応急対応は疾患により異なります。自己判断での処置は避け、症状が強い/拡大する/痛む場合は医師に相談してください。
一般的な点状角質融解症に使われる薬
① 【抗菌薬の外用薬(第一選択)】
▶ コリネバクテリウム属などに有効な外用抗菌薬
フシジン酸 フシジンレオ軟膏 グラム陽性菌に有効、第一選択
ゲンタマイシン ゲンタシン軟膏 広く使用される抗菌薬、比較的安全
クリンダマイシン ダラシンTゲル(にきび薬としても使用) 耐性菌の心配があるため限定的に使用される
ナジフロキサシン アクアチムクリーム にきびなどにも使われる、抗菌スペクトル広め
🔸 1日1~2回塗布。数日~1週間ほどで改善することが多いです。
🔸 塗布後は乾燥を保ち、通気性を良くする工夫が重要。
② 【重症・再発例には内服抗菌薬】
セファレキシン ケフレックス 安全性高く、外用で不十分な場合に使用
クラリスロマイシン クラリス 抗菌スペクトル広く、においの原因菌にも効果
🔸 内服は通常3〜7日間程度。
③ 【補助療法・予防的対策】
▶ 殺菌・消毒薬(補助的に使用)
クロルヘキシジン(ヒビテン液など)
ベンザルコニウム(オスバンなど)
イソジン消毒液(ただし刺激性あり)
▶ 制汗・乾燥剤(再発予防に重要)
塩化アルミニウム液 オドレミン、パースピレックスなど 足の多汗対策に。市販あり。
足用制汗スプレー Agデオ24、8×4、デオナチュレなど 市販可。補助的に使用可。
❌ 効果がない or 禁忌の薬
薬剤 理由
ステロイド外用薬単独 炎症を抑えるが細菌感染を悪化させる恐れ
抗真菌薬(白癬薬) 真菌ではなく細菌感染症なので無効
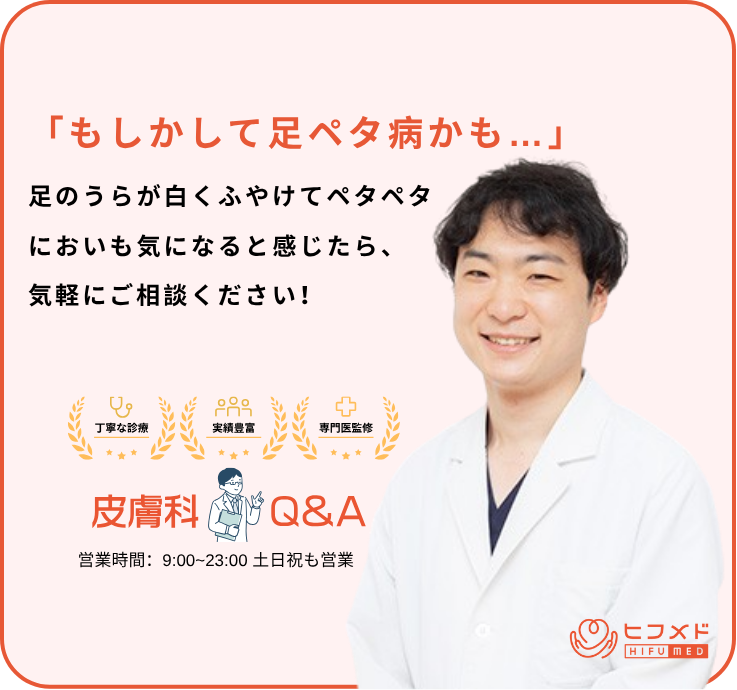
診断と検査
✅ 多くは視診(見た目)で診断が可能
✅ 必要に応じて細菌培養・ウッド灯・真菌検査(KOH)などを行います
✅ 足白癬と合併することもあるので、両方の治療が必要な場合も
「点状角質融解症【足ペタ病】」と似ている症状の病気(鑑別疾患)
手湿疹(主婦湿疹)
手全体にカサカサ・ひび割れ・かゆみ 水ぶくれよりも乾燥とひび割れが中心/手荒れや水仕事がきっかけに
白癬(足の水虫)
足の裏や指の間にジュクジュク・皮むけ・かゆみ 真菌検査(KOH検査)でカビが検出/かゆみが強く慢性化しやすい
接触皮膚炎
アレルギー物質・刺激で皮膚に赤み・水ぶくれ 原因物質がはっきりしている/範囲がくっきりしていることも
膿痂疹(とびひ)
水ぶくれが破れてかさぶたに/子どもに多い 細菌感染が原因/うつることも
汗疹(あせも)
細かい赤いブツブツ/かゆみ中心 背中・首に多く、手足にはあまり出ない/赤くかゆいが水疱は少ない
掌蹠膿疱症
手のひらや足の裏にうみをもったしこりが出る 繰り返し膿疱が出現/関節症状を伴うことも
点状角質融解症【足ペタ病】の特徴をチェック!
◻︎ 強い痛みや発熱がある
◻︎ 点状というより「傷・潰瘍・壊死」に近い見た目がある
◻︎ 糖尿病などがあり、足の傷が悪化している(足壊疽・膿瘍が疑われる)
▶︎ これらに当てはまれば、「点状角質融解症【足ペタ病】」や関連する疾患の可能性があります
⚠️緊急度をチェック!
◻︎ 薬中止で再発を繰り返す
◻︎ 長年持続し拡大、ステロイド無効(別疾患の可能性)
▶︎ 1つでも当てはまれば受診/オンライン相談を
友達登録は無料
受診の目安(タイムライン)
当日〜翌日:強い痛み・発熱、潰瘍様の見た目、糖尿病などで悪化が疑われる
早めに受診:足裏が白くふやけてベタつく/悪臭/点状の穴が多数、水虫薬で改善しない
迷ったら相談:鑑別がつかない、再発を繰り返す、学校・仕事に支障がある
予防のポイント
足を毎日しっかり洗い、特に指の間をよく乾かす
靴はローテーションし、内部を乾燥させる
吸汗速乾素材・通気性のよい靴下に替える
靴内の抗菌スプレーや中敷きの除菌を取り入れる
共同のスリッパや足拭きマットの共用を避ける
FAQ
Q1. 水虫の薬で治りますか?
Q2. どのくらいで良くなりますか?
Q3. 家でできるケアはありますか?
Q4. 検査は必要ですか?
医師
山田 貴博 Yamada Takahiro
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
監修薬剤師/公衆衛生学修士
畔原 篤 Atsushi Azehara
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
執筆者
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






