20代 女性のご相談
ポルフィリン症ってどんな病気?

医師の回答
ポルフィリン症(ポルフィリア)は、血液の材料である「ヘム」を作る途中で必要な酵素の働きがうまくいかず、体に有害な物質(ポルフィリン類など)がたまってしまう病気です。
〜光に当たると皮ふが痛い…?血の材料がうまく作れない、体の中の工場トラブル〜
ポルフィリン症(ポルフィリア)とは、体の中で「血液の材料(ヘム)」を作るときに必要な酵素のはたらきが弱い・足りないことで起こる、先天性の代謝異常の病気です。ポルフィリン症とは、ポルフィリン代謝に関わる酵素異常によって、ポルフィリンやその前駆体が体内に蓄積し、多彩な症状を引き起こす疾患の総称です。主に急性型(急性間欠性ポルフィリン症〔AIP〕など)と皮膚型(ポルフィリン症カットネア〔PCT〕、先天性エリトロポイエティックポルフィリン症〔CEP〕など)に分けられます。急性型では腹痛や神経症状を主体とし、皮膚型では光線過敏に伴う水疱やびらんが特徴です。遺伝的背景に加え、薬剤やホルモン、ストレスが発症の誘因となることが知られています。
たとえば、急性型は腹痛・便秘・精神症状・末梢神経障害を呈し、重症例では呼吸筋麻痺に至ることがあります。皮膚型では手背や顔など光にさらされる部位に水疱、瘢痕、色素沈着が出現し、二次感染や瘢痕化を残すことがあります。
主な原因
ポルフィリン代謝酵素の遺伝的異常
薬剤(バルビツール酸系、ホルモン剤など)の誘発作用
アルコールや鉄過剰による肝障害
紫外線曝露による皮膚への影響
ホルモン変動や精神的ストレス
急性型は思春期以降の女性に多く、ホルモン周期や薬剤で誘発されやすい傾向があります。皮膚型は中高年男性に多く、特に肝疾患やアルコール摂取と関連する例が多くみられます。好発部位は顔、手背、前腕など日光に当たりやすい場所です。
経過としては、急性型では突発的な発作が数日持続し、神経後遺症を残すこともあります。皮膚型では慢性的に皮疹が繰り返され、瘢痕や手指の変形に進行することもあります。悪化因子としては薬剤、飲酒、紫外線、感染、ストレスなどが関わります。早期に受診し適切に管理することで、発作や皮膚障害を軽減し生活の質を維持できます。
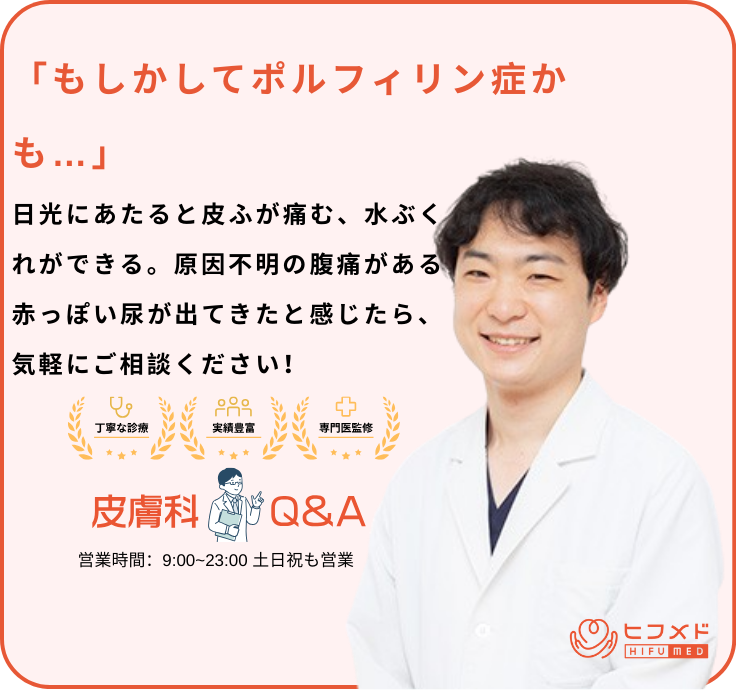
✅ ポルフィリン症に使われる治療薬・管理法
◆ 急性型(AIPなど)
治療法 内容
発作時の第一選択:ヘミン静注(ヘムアルブミン製剤) 国内では「ノーモヒメン®」(輸入薬)/ALA合成を抑制して発作を止める
ブドウ糖大量静注 肝臓でALA合成を抑えるための代替手段(ヘミンが使えない場合)
対症療法 痛み:鎮痛薬(非NSAIDs)/精神症状:ベンゾジアゼピンなど/低ナトリウム:電解質補正
発作予防(慢性型) 月1回の定期ヘミン投与やホルモン調整(女性)/薬剤・ストレスの回避が重要
◆ 皮膚型(PCT・CEPなど)
治療 内容
紫外線対策(最重要) 長袖・帽子・UVカット/屋内作業中心の生活
瀉血療法(鉄過剰対策) PCTでは鉄代謝異常が関与 → 月1回瀉血で改善
低用量ヒドロキシクロロキン ポルフィリン排泄促進(ただし肝障害に注意)
肝疾患治療 C型肝炎やアルコール性肝障害の併発に対処
保湿・外用療法 水疱や痂皮に対してワセリン・抗菌薬外用などで二次感染予防
🔬 病院で何を調べるの?
視診・問診:症状の出方や発作時期、家族歴、薬剤歴を確認することで、急性型か皮膚型かを大まかに判断します。皮疹の分布や腹痛の特徴が重要です。
尿検査(ポルフォビリノーゲン・ALA定量):急性発作時に上昇するため、診断に直結します。発作中に採取し、感度が高い点が特徴です。
血液検査:肝機能、鉄代謝(フェリチン・トランスフェリン飽和度)、炎症マーカーなどを調べます。PCTでは鉄過剰が診断の手がかりになります。
遺伝子検査:酵素遺伝子の変異を確認し、サブタイプ分類や家族への遺伝カウンセリングに役立ちます。結果は数週間かかることがあります。
皮膚生検:皮膚型で病理学的にポルフィリン沈着や水疱の特徴を確認します。局所麻酔下で行われ、小さな瘢痕が残る可能性があります。
- 画像検査(腹部エコー・MRIなど):肝疾患や腫瘍の合併を評価するために行います。特にPCTではC型肝炎や肝細胞癌リスクを調べる目的があります。
🔬 間違えやすい他の病気(鑑別)
アレルギー性紫斑病(IgA血管炎)
⇒四肢に紫斑、腹痛や腎症状を伴う急性の血管炎。皮膚は紫斑中心で、ポルフィリン症の水疱や光線過敏とは異なる。酵素異常はない。
被角血管腫(アンギオケラトーマ)
⇒赤紫色の小結節が皮膚に出る良性腫瘍。単発が多く、体内に物質が蓄積する病気ではない。全身の臓器障害も伴わない。
多発性神経炎(Charcot-Marie-Tooth病など)
⇒手足のしびれや筋力低下が進行する神経疾患。神経症状は似るが、ポルフィリン症のような腹痛や皮膚症状はなく、家族歴が手がかりになる。
ライソゾーム病(ゴーシェ病・ポンぺ病など)
⇒酵素欠損で肝脾腫や骨障害などを起こす代謝異常症。皮膚の光線過敏や水疱はみられず、酵素活性検査で鑑別可能。
熱中症・自律神経失調症
⇒発汗異常や体温調節不良が主体。ポルフィリン症のような慢性進行はなく、一過性で皮膚の血管腫や水疱は出ない
予防のポイント 紫外線を避けるため日焼け止めや衣類で皮膚を保護する 禁酒や節酒を心がけ肝臓への負担を減らす 鉄分の過剰摂取を控え、医師管理下での瀉血を行う 発作を誘発する薬剤を避ける(服薬前に確認する) 睡眠を十分に取り、精神的ストレスを軽減する 女性は月経周期に伴う症状変動に注意し、ホルモン管理を行う 水疱や痂皮は掻かず、保湿や外用薬で皮膚を守る 定期的に血液検査や肝機能評価を受ける
<参考資料>
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






