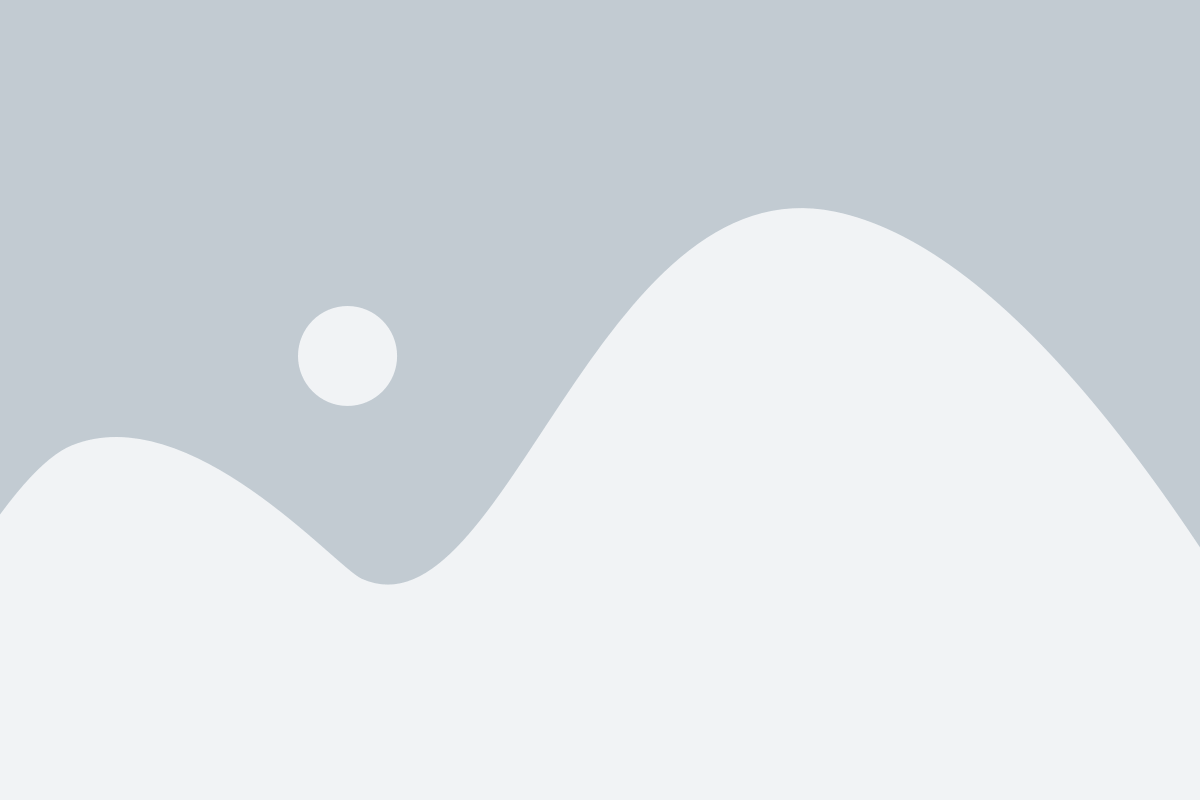10代 男性のご相談
足白癬(みずむし)ってどんな病気?

医師の回答
足白癬は「みずむし」とも呼ばれ、白癬菌(はくせんきん)というカビ[真菌(しんきん)]が足の皮膚に寄生することで起こる感染症です。


〜かゆみや皮むけの正体は“カビ”かも!?〜 みずむしは、白癬菌(はくせんきん)というカビの仲間が足の皮ふに感染して起こる病気です。 主に 足の指の間 や 足のうら・かかと にあらわれます。 かゆくなったり、皮がむけたり、水ぶくれができることもあります。 でも実は、かゆくない「気づきにくいタイプ」もあるので要注意⚠️
白癬菌は、あたたかくてジメジメしたところが大好き!
汗で蒸れた足や、通気性の悪い靴の中はまさに天国 🌈
みずむしは一年中うつる可能性があるけど、とくに梅雨〜夏は汗も増えて、悪化しやすい季節です!
また、ジム・プール・銭湯などの床、家のスリッパやバスマットを通じて感染することもあります。
みずむしは、タイプによって見た目や場所が少し違います
1. 足の指の間がジュクジュクしたり、皮がむける 趾間型(しかんがた)
2. 土ふまずなどに小さな水ぶくれがポツポツ 小水疱型(しょうすいほうがた)
3. かかとの皮ふが分厚くなってカサカサ・ひび割れ 角質増殖型(かくしつぞうしょくがた)
※靴を長時間はいている人(運転・営業・調理の仕事など) 男性に多い(特に40代〜)
高齢の方、糖尿病のある人、体の抵抗力が下がっている人 家族にみずむしの人がいると、うつるリスクがUPします。
みずむしは、市販薬や病院のくすり(抗真菌薬)で治せます!
ただし、見た目だけ良くなっても中の菌は残っていることもあるので、自己判断でやめずに、最後までしっかり塗り続けることが大切です
💊 外用薬(塗り薬)※軽症~中等症に使用
- ラミシール(テルビナフィン)
- ルリコン(ルリコナゾール)
- ペキロン(ラノコナゾール)
- ゼフナート(セチリスタット)
- アスタット(ストレブトリマイシン)
- マイコスポール(ビホナゾール)
- ニゾラール(ケトコナゾール)
※市販薬にも類似成分を含むものがあります(例:ラミシールAT、ブテナロック、ダマリンLなど)
💊 内服薬(飲み薬)※広範囲、爪白癬合併例、外用で効果が乏しい場合など
- ラミシール錠(テルビナフィン)
- イトリゾール(イトラコナゾール)
- ネイリン(ホスラブコナゾール)

🔬 病院で何を調べるの?
足白癬かどうかを調べるには「KOH検査(顕微鏡検査)」を行います🧪
皮膚の表面のカケラを取って、白癬菌(カビ)がいるかをチェックします。
数分で結果がわかりますので、気軽にご相談ください
みずむし(足白癬)と間違えやすい病気って?
「これ、みずむしかな?」と思っても、実は別の病気だった!ということもあります⚠️
- 異汗性湿疹(いかんせいしっしん) 小さな水ぶくれが足の裏や側面に出る 左右対称に出ることが多い/真菌検査は陰性
- 接触皮膚炎(かぶれ) 靴や洗剤などの刺激で赤くただれる 原因物質がはっきりしていて、かゆみが急に出る
- 乾燥性湿疹(皮脂欠乏性湿疹) 足全体が乾燥してカサカサ、かゆい 水ぶくれはなし/季節で悪化しやすい(冬)
- 細菌感染(膿痂疹など) 皮膚が赤く腫れて膿がたまる 真菌ではなく細菌が原因、抗生物質で治療
- 掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう) 足の裏・手のひらにうみをもったぶつぶつが繰り返し出る 膿疱が固くて痛い/菌は検出されない
- 魚の目・タコ 歩くところに固い角質ができる かゆみはなし/押すと痛いのが特徴
予防のポイント
足は毎日ちゃんと洗って、よく乾かす
靴下はこまめに替える&毎日洗う
靴はできれば毎日ローテーション
家族でタオル・スリッパの共用はNG!
<参考資料>
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。