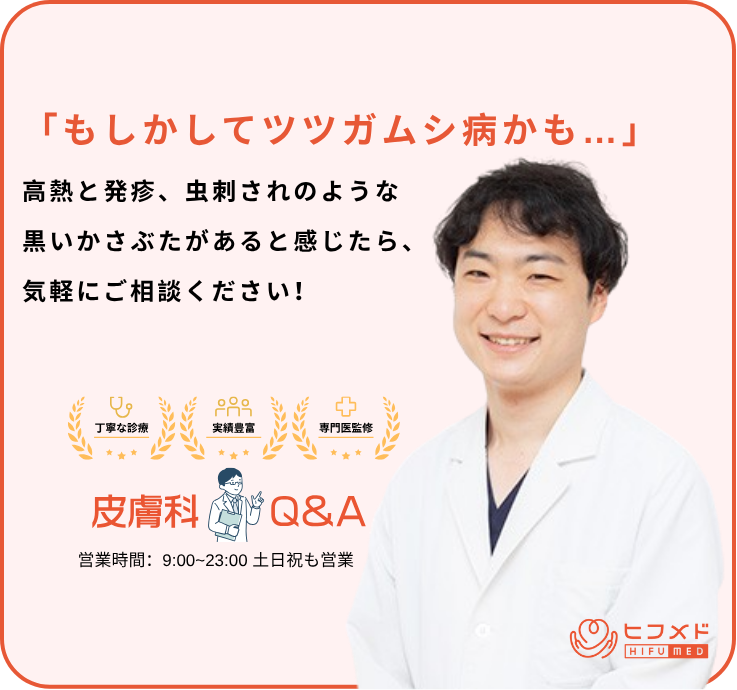40代 男性のご相談
ツツガムシ病ってどんな病気?

医師の回答
ツツガムシ病は、ツツガムシに刺されることによって引き起こされる病気です。 ツツガムシに刺されると、5~14日で悪寒や頭痛を伴った40℃前後の発熱があらわれます。
〜高熱と発疹、虫刺されのような黒いかさぶた…それ、ツツガムシ病かも!?〜 ツツガムシ病は、ツツガムシに刺されることによって引き起こされる病気です。
ツツガムシに刺されると、5~14日で悪寒や頭痛を伴った40℃前後の発熱があらわれます。
主にからだや陰部、わきの下に、直径1~2cmの赤い発疹[紅斑(こうはん)]と中心が黒色のかさぶたの刺し口がみられます。
症状が出てから2~7日後に、2~5mmの淡い紅色の発疹がからだ中に広がり、7~10日でなくなります。
日本では、北海道や沖縄を除く全国で症例の報告がありますが、関西に少なく、北関東に多いといった地域性があります。
ツツガムシ病は、ツツガムシと呼ばれるダニの仲間に刺されることによって発症する感染症で、日本では秋から初冬にかけて多く発生します。特に野山や草むら、河川敷などでの作業やレジャー後に高熱や発疹が出た場合、この病気の可能性があります。刺されてから症状が出るまでに少し時間が空くこともあり、「風邪かな?」「インフルエンザかも」と見過ごされがちですが、早期の診断と治療が非常に重要です。
この病気の原因となるのは、「ツツガムシ病リケッチア(Orientia tsutsugamushi)」という細菌の一種です。これを保有しているツツガムシ(0.2mmほどの小さなダニ)に刺されることで、体内にリケッチアが侵入し、発症します。ツツガムシという名前の虫がいるわけではなく、リケッチアをもった特定のダニが感染源となるのが特徴です。
症状としては、刺されてから5〜14日後に突然の高熱(38〜40℃)が現れます。同時に、倦怠感・頭痛・筋肉痛・リンパ節の腫れなどの全身症状も出ることが多く、体力を奪われます。最も特徴的なのが「刺し口」で、直径1~2cmほどの赤みを帯びた紅斑の中央に、黒いかさぶた状の潰瘍(5mm程度)が見られる点です。この刺し口はわきの下や股、腹部、陰部など目立たない場所にできることが多いため、見逃されがちです。その後、2〜7日以内に淡い紅色の細かい発疹が全身に広がり、7〜10日ほどで消失します。
日本では北海道や沖縄を除く全国でツツガムシ病の報告がありますが、地域差もあり、北関東や中部地方での発生が多く、関西では比較的少ないとされています。特に農作業や林業に従事している方、登山・キャンプ・釣りなどのレジャーで自然の中に入る方、公園や草地の手入れをしている方などがリスクの高い環境にいます。
治療は、トラサイクリン系抗生物質(主にドキシサイクリンなど)の内服が基本です。適切に薬を服用すれば、投与開始から1〜2日で解熱し、症状も次第に改善していきます。ただし、重症化してしまうと肺炎や脳炎などを引き起こすこともあり、早期診断と早期治療が命を守る鍵になります。高熱が続き、一般的な風邪薬や解熱剤で改善しない場合には、専門医の診察を受けることが大切です。
予防のためのワクチンは現在存在しないため、ダニに刺されないための対策が最も重要です。野外での活動時には、長袖・長ズボン・手袋・帽子などで肌の露出を避け、ズボンの裾を靴下や長靴の中に入れてダニの侵入を防ぎましょう。また、ディートやイカリジンを含む虫よけスプレーも有効です。活動後にはすぐに入浴し、全身の皮膚を鏡でチェックすることで、刺し口の早期発見につながります。
「草むらに入ったあとに高熱と発疹が出てきた」「虫刺されのような黒いかさぶたが気になる」「風邪やインフルエンザと診断されたけど熱が下がらない」など、症状に心当たりがある場合には、自己判断せずに医療機関を受診してください。ツツガムシ病は、適切な抗生物質で十分に治療可能な病気ですが、放置すると命に関わるリスクもあります。
🔬 病院で何を調べるの?
① 医師による問診・視診(見た目のチェック)
症状の経過(いつから発熱・発疹があるか)
最近、野外(草むら・畑・山など)に入ったか
全身の発疹の有無や分布
特有の「刺し口」(黒いかさぶた)の有無
わきの下、腹部、陰部、股のつけ根など、人目につきにくい場所も確認します(患者さん自身のセルフチェックも大事です)
この「刺し口」+「高熱+発疹」という組み合わせが、ツツガムシ病の強い手がかりになります。
② 血液検査(必要に応じて)
ツツガムシ病の診断確定や重症度を把握するために、以下の血液検査を行うことがあります:
炎症の程度(CRP、白血球数など)
肝機能・腎機能の異常の有無(AST, ALT, クレアチニンなど)
リケッチア感染の抗体検査(間接蛍光抗体法など)※一部の施設で実施
リケッチアに対する抗体は、感染から数日たたないと検出されないこともあります。
症状と刺し口が典型的な場合は、検査結果を待たずに治療を開始することもあります。
③ 必要に応じて画像検査(重症例)
肺炎や臓器合併症が疑われるときは、
胸部レントゲン検査
CT検査
などを行うこともあります。
④ 診断後は治療へ(診断がついたらすぐ治療)
典型的な症状がそろっていれば、早期に抗菌薬(ドキシサイクリンなど)の内服を開始します。
発熱や倦怠感が強い場合、または内服困難な方には点滴治療や入院管理を行うこともあります。
🔍 ツツガムシ病と間違えやすい疾患(類似疾患)
日本紅斑熱
⇒リケッチア感染/発熱+発疹+刺し口 症状が酷似!/違いは発症地域や重症度/刺し口が目立たないことも
デング熱
⇒高熱・頭痛・筋肉痛/発疹も出る 刺し口は目立たず、海外渡航歴が多い/血小板減少が目立つ
ノミ・ダニ咬傷
⇒赤い発疹・かゆみ/複数個所に見られる 発熱・全身症状がない/刺し口にかさぶた形成はまれ
敗血症・感染性心内膜炎
⇒高熱・倦怠感・点状出血 基礎疾患あり/皮膚の発疹が細かく散在/刺し口なし
薬疹(薬による発疹)
⇒発熱と発疹を伴う/薬の服用歴あり 左右対称の発疹/刺し口や黒いカサブタはなし
SLE(全身性エリテマトーデス)
⇒発熱・発疹・関節痛など多彩な症状 自己免疫疾患/慢性経過・多臓器に影響/リケッチア陰性
ツベルクリン反応陽性結核性紅斑
⇒発熱+皮疹/慢性の結核感染あり 全身症状が長期的・刺し口はなし/検査で結核菌陽性
予防のポイント
ツツガムシ病にはワクチンが存在しないため、「刺されないこと」が唯一の予防策です。
特に秋〜初冬(10〜12月)に野外で活動する方は、以下の対策をぜひ実践してください。
【服装の工夫で刺されにくく】
長袖・長ズボン・手袋・帽子など、肌の露出をできるだけ避ける
首元や手首・足首などのすき間をタオルやゴムでカバーする
ズボンの裾は靴下や長靴の中に入れる(ダニが侵入しにくくなります)
【虫よけを活用】
ディートまたはイカリジンが配合された虫よけスプレーを使用
肌だけでなく、服の上からも噴霧してダニの接近を防ぐ
活動時間が長い場合は、数時間ごとにこまめに塗り直しましょう
【活動後のセルフチェックとケア】
帰宅後はすぐに入浴して、皮膚についたダニや病原体を洗い流す
特に、わきの下・股・腹部・陰部など、刺し口ができやすい場所をチェック
鏡を使って全身を確認すると、黒いかさぶた(刺し口)の早期発見につながります
【野外活動の環境に注意】
草むら、あぜ道、河川敷、藪の中にはできるだけ立ち入らない
やむを得ず入る場合は、防虫対策を徹底
休憩するときは地面に直接座らず、レジャーシートを使用
【農作業・林業の方は特に注意】
秋の作業シーズン中は、毎日の体調管理と皮膚チェックを習慣に
家族や同僚の異変にも気づけるよう、ツツガムシ病の症状を共有しておくことも大切です
<参考資料>
- 2010年:名古屋市立大学医学部 卒業
- 2010年:NTT西日本大阪病院、阪南中央病院にて研修
- 同年:大阪大学大学院医学系研究科 神経細胞生物学講座にて基礎医学研究に従事
- 2015年:阪南中央病院皮膚科 勤務
- 2017年:天下茶屋あみ皮フ科クリニック 開業
- 2024年:AMI SKIN CLINIC 開設
- 2025年:東京駒込皮膚科クリニック 開業
皮膚のトラブルは、見た目の悩みだけでなく、痒みや痛みによって日常生活の質(QOL)を大きく下げてしまうものです。「こんな些細なことで相談してもいいのかな?」とためらわず、ぜひお気軽にご相談ください。
丁寧な診察と分かりやすい説明を心がけ、地域の皆さまの「肌のホームドクター」として、健やかな毎日を全力でサポートさせていただきます。
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。