20代 女性のご相談
おむつ皮膚炎ってどんな病気?

医師の回答
おむつで覆われた部位の皮膚が炎症を起こし、赤くなったりただれたりする皮膚トラブルのことで、特に生後0〜2歳ごろの赤ちゃんに多く見られます。赤ちゃんの皮膚は大人に比べて非常に薄く、バリア機能が未熟なため、ちょっとした刺激でも炎症を起こしやすくなっています。

おむつ皮膚炎の原因はさまざまですが、最も多いのは、汚れたおむつを長時間つけたままにしてしまうことで起こる皮膚への刺激です。尿や便の成分によって皮膚が刺激されるほか、ムレによって皮膚がふやける「浸軟(しんなん)」が起こり、さらにおむつの摩擦やおしりふき、石けんなどの刺激が加わることで炎症が悪化します。また、皮膚のバリアが壊れた状態が続くと、カンジダといった真菌(カビ)が増殖し、二次感染を起こすこともあります。このような場合には、「乳児寄生菌性紅斑」との鑑別も必要になります。
症状としては、赤く広がる発疹(紅斑)、小さなブツブツ(丘疹)、ジュクジュクしたただれ(びらん)などが挙げられます。さらに進行すると、赤ちゃんが強い痛みを感じて泣いたり、おむつ替えを嫌がったりすることもあります。白っぽいポツポツが見られる場合には、真菌感染が疑われるため、早めの治療が大切です。
おむつ皮膚炎が起こりやすい部位は、おしりや股のあいだ、太もものつけ根、性器まわりなど、おむつが接触するすべての部位です。特に、汗をかきやすい夏場や、離乳食が始まってうんちの回数が増える時期、下痢や風邪のとき、夜間などおむつ替えの間隔が空きやすいときには注意が必要です。また、強くこすってしまうおしりふきの使用も悪化の原因になります。
おむつ皮膚炎を防ぐには、こまめなおむつ交換と、やさしいスキンケアが基本です。おしりはぬるま湯でやさしく洗い、完全に乾かしてからおむつをつけるようにします。必要に応じて、ワセリンや亜鉛華軟膏などで保護膜をつくると効果的です。症状がある場合は、炎症を抑えるステロイド外用薬や、カンジダ感染が疑われる場合には抗真菌薬が処方されることもあります。一時的におむつを外して皮膚を乾かす時間をつくるのも有効です。
おむつ皮膚炎は適切なケアで改善することが多いものですが、次のような症状が見られる場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
赤みが日に日に強くなったり、発疹が広がってきたりする場合には、炎症が悪化している可能性があります。また、赤いブツブツ(丘疹)が周囲にまで広がってきた場合や、塗り薬を使用しても効果が見られず、皮膚がジュクジュクと湿った状態になっているときも注意が必要です。
さらに、発熱を伴ったり、患部から膿が出てきたり、赤ちゃんが痛がって触られるのを嫌がるような場合には、感染症を併発している恐れもあります。これらの症状が見られるときは、自己判断でのケアを続けず、できるだけ早く皮膚科や小児科を受診してください。
おむつ皮膚炎は通常、適切なケアを行えば数日で改善することが多いですが、1週間以上経っても症状が改善しない場合も、何らかの別の疾患が隠れている可能性があるため、専門医の診察を受けることが大切です。
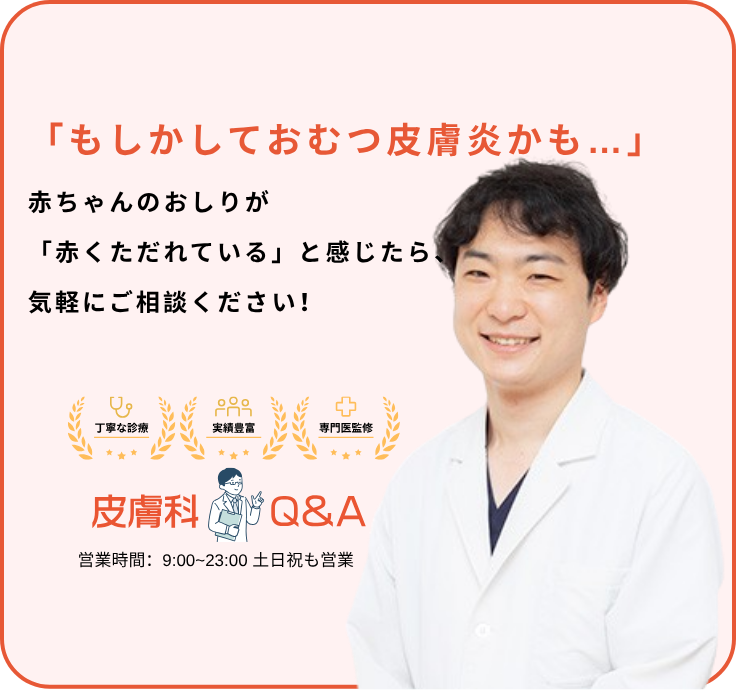
【💊主な治療薬】
① 【基本治療:保護+保湿】
薬剤・製品 内容
亜鉛華軟膏 刺激から皮膚を保護し、治癒を促進
プロペト/ワセリン 皮膚のバリア機能を補う
アズノール軟膏(ジメチルイソプロピルアズレン) 抗炎症・組織修復作用あり
ベビーワセリン 乳児用の低刺激保湿剤
② 【炎症が強い場合:ステロイド外用薬(短期間)】
ステロイド薬 商品名の例 注意点
ヒドロコルチゾン ロコイド軟膏 比較的弱く、安全性が高い
プレドニゾロン プレドニン軟膏など 医師の指示で短期使用
おむつ内は吸収が良いため、強いステロイドは避ける。数日間の短期使用が原則です。
カンジダ性おむつ皮膚炎(白いカス・境界がはっきり・盛り上がった発疹が特徴)
薬剤 ・商品名 目的
ニゾラールクリーム(ケトコナゾール) 真菌(カンジダ)を抑える
ゲンタマイシン ゲンタシン軟膏 黄色ブドウ球菌などの感染対策
フシジン酸軟膏 フシジンレオ軟膏 黄色ブドウ球菌などの感染対策
③ 【感染を伴う場合】
ラミシールクリーム(テルビナフィン) 真菌(カンジダ)を抑える
細菌感染(ジュクジュク、膿があるとき)
実は見た目がそっくりでも、治療法が全然ちがうこともあるんです!
「かゆい」「赤くてジュクジュクする」「ずっと治らない」それ、本当にアトピー性皮膚炎でしょうか?
- よくある湿疹タイプ
- 接触皮膚炎(かぶれ):
金属や化粧品などに触れて赤くなる。触れた部分だけに出ることが多いよ。 - 皮脂欠乏性湿疹:
乾燥による湿疹。特に冬にスネなどにカサカサが出ることが多い! - 手湿疹(手あれ):
手をよく洗う人・水仕事が多い人に。アトピーと勘違いされがち。あせも 暑い時に出るぶつぶつ。汗のかきすぎが原因。 - 貨幣状湿疹:
丸くて赤い湿疹ができる。水虫とそっくりなこともあるので注意! - 乾癬(かんせん):
赤くてカサカサ、白い粉がふいたような湿疹が出る。アトピーより皮膚が厚くてかゆみが少なめなのが特徴です。薬が効かないときは、乾癬の可能性もチェック! - 白癬(はくせん)水虫:丸く広がる赤みはアトピーと間違えられがち!
- 疥癬(かいせん): ダニが原因で、夜にかゆみが強くなる。家族にもうつりますとびひ かいた所からばい菌が入って広がる。黄色いかさぶたがヒント!
- 免疫の病気:皮膚だけじゃなく、熱や下痢など体調全体に影響が出ます。
- 「ずっと湿疹だと思っていたら、実は皮膚のリンパ腫(がん)だった」そんなケースもあります。
こんなときは、皮膚の一部を調べる検査(皮膚生検)をおすすめします。
・湿疹が左右で違う場所に出るステロイドや保湿剤がまったく効かない発熱・だるさなど全身症状がある
・家族にもうつっている
・赤ちゃんが全身真っ赤になっている
ひとつでも当てはまったら、おむつ皮膚炎じゃないかもしれません!
気になる方は、皮膚科での検査・診察を受けてみましょう
監修薬剤師/公衆衛生学修士 畔原 篤Atsushi Azehara
新潟薬科大学卒業。筑波大学大学院 公衆衛生学学位プログラム修了(修士)
ウエルシア薬局にて在宅医療マネージャーとして従事し、薬剤師教育のほか、医師やケアマネジャーなど多職種との連携支援に注力。在宅医療の現場における実践的な薬学支援体制の構築をリード。2023年より株式会社アスト執行役員に就任。薬剤師業務に加え、管理業務、人材採用、営業企画、経営企画まで幅広い領域を担当し、事業の成長と組織づくりに貢献している。さらに、株式会社Genonの医療チームメンバーとして、オンライン服薬指導の提供とその品質改善にも取り組むとともに、医療・薬学領域のコンテンツ制作において専門的なアドバイスを行っている。経済産業省主催「始動 Next Innovator 2022」採択、Knot Program 2022 最優秀賞を受賞。
執筆者
ヒフメドの編集チームは、皮膚疾患で悩む方に向けて専門的かつ最新の情報を分かりやすく届けることを目指しています。
アトピーや皮膚感染症といった疾患の基礎知識から、治療・生活管理の実用的なコツ、最新の治療事情まで幅広くカバー。読者が記事を読むことで「すぐに役立てられる」情報提供を心がけています。






